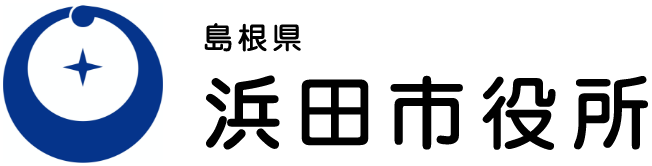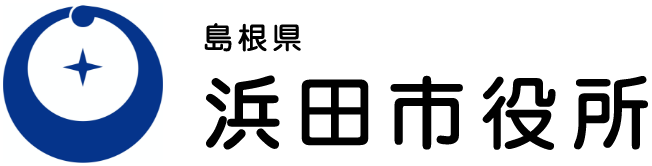高額療養費について
医療費が高額となった場合に、世帯内で合算して下表の医療費自己負担限度額(月額)を超えた額が、申請により支給される制度です。支給申請の対象となる人には、後日、市から通知します。
限度額適用認定について
医療機関の窓口での個人の支払いを自己負担限度額で止める制度です。
マイナ保険証(健康保険証を登録したマイナンバーカード)であれば提示のみで止まるため、申請は不要です。
マイナ保険証を利用しない人は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受け、「資格確認書」と併せて提示する必要があります。ただし、70歳以上で所得区分が「現役並み所得者Ⅲ」又は「一般」の人は、「資格確認書」の提示のみで止まるため、「限度額適用認定証」の交付を受ける必要はありません。
医療費自己負担限度額(月額)
入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療と認められないものについては、自己負担限度額の計算対象となりません。
70歳未満の人と70歳以上の人の両方がいる世帯については、70歳以上の自己負担限度額を適用した後に70歳未満の自己負担限度額に合算して適用します。
| 所得区分 | 所得金額(注1) | 自己負担限度額(月額) | ||
| 3回目まで | 4回目以降(注2) | |||
|
住民税 課税世帯 |
901万円を超える世帯 | ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 600万円を超え901万円以下の世帯 | イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
| 210万円を超え600万円以下の世帯 | ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
|
210万円以下の世帯 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 | 44,400円 | |
| 住民税非課税世帯(注3) | オ | 35,400円 | 24,600円 | |
※個人の自己負担額が限度額に達しない場合は、同じ月内に自己負担額21,000円以上の支払いが2回以上になった場合のみ、それらを合算して限度額を超えた部分が支給されます。
70歳以上75歳未満の人
| 所得区分 | 割合 | 自己負担限度額世帯単位 | |||||
| 外来(個人ごと) |
外来+入院 |
||||||
|
現役並み 所得者 |
Ⅲ | 課税標準額が690万円以上(注4) | 【3割】 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降は140,100円) |
|||
| Ⅱ | 課税標準額が380万円以上(注4) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降は93,000円) |
|||||
| Ⅰ | 課税標準額が145万円以上(注4) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降は44,400円) |
|||||
| 一般 | 住民税課税世帯で課税標準額が145万円未満(注5) | 【2割】 |
18,000円 年間限度額144,000円(注6) |
57,600円 (4回目以降は44,400円) |
|||
| 低所得者 | Ⅱ | 住民税非課税世帯(注7) | 8,000円 | 24,600円 | |||
| 低所得者 | Ⅰ | 住民税非課税世帯(注8) | 8,000円 | 15,000円 | |||
※世帯内の合算については、一般・低所得者区分であり、ひと月に外来受診だけの場合は、被保険者個人ごとに自己負担限度額を計算し、なお残る自己負担額について合算して計算します。入院を含む場合は、すべて合算して計算します。
共通項目
窓口での自己負担限度額の計算方法
入院時食事代
入院時に支払う食事代は以下のとおりです。
なお、所得区分が「住民税非課税世帯オ」又は「低所得者Ⅱ」に該当し、過去12か月で91日以上の入院がある人は、マイナ保険証の有無に関わらず、食事代の更なる減額のために長期入院該当の認定を受ける必要があります。領収書など入院期間がわかるものを持って申請してください。
| 所得区分 |
過去12か月 入院日数 |
1食につき |
長期入院該当 認定申請 |
|
住民税課税世帯ア~エ 現役並み所得者、一般 |
- | 510円 | 不要 |
|
住民税非課税世帯オ 低所得者Ⅱ |
90日以下 | 240円 | 不要 |
| 91日以上 | 190円 | 必要 | |
| 低所得者Ⅰ | 110円 | 不要 | |
療養病床に入院したときの食費・居住費
療養病床に入院している65歳以上の人の食事代は以下のとおりです。また、居住費として1日あたり370円の負担があります。
○65歳以上75歳未満の人
| 所得区分 | 1食につき |
| 住民税非課税世帯(オ) | 240円 |
| 低所得者Ⅱ | |
| 低所得者Ⅰ | 140円 |
認定にかかる注意
認定期間は、申請日の属する月の1日から次の7月31日までです。
8月以降も引き続き認定を受けるためには、再度申請が必要です。
保険料に滞納がある場合は、認定できません。
すべての申請に必要なもの
〇世帯主及び申請対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
※住民票上同一世帯の人でない人が窓口に来られる場合は、委任状が必要となります。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 保険年金課
-
-
電話番号:0855-25-9410
-