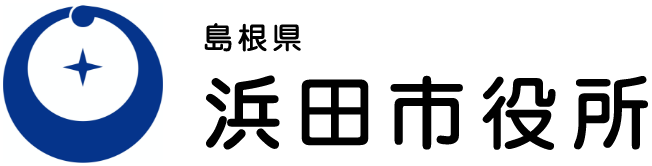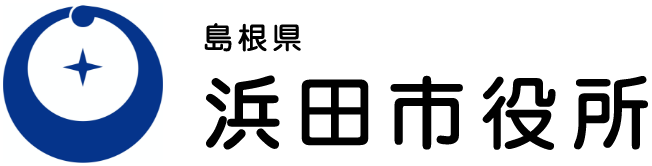浜田市の歴史
| 代 区分 |
日本のできごと | 浜田のできごと | ||||
| 文化の動き | ||||||
| 旧石器 | 約1万年前 | 日本列島が形成される | 石見の各地でも旧石器人がナイフ形石器や石槍で狩猟活動を展開(岩塚【2】遺跡(金)) | |||
| ○狩りと漁、採集の生活 | 縄文土器 | |||||
| 縄文 | 竪穴住居 | |||||
| 土偶・貝塚 | ||||||
| 縄文「むら」が営まれる(日脚遺跡(浜)など) | ||||||
| 弥生 | 前300年頃 | 稲作が伝わる | 弥生土器 | 各地に最初の農村が誕生(鰐石遺跡(浜)、七渡瀬遺跡群(金)など) | ||
| 高床倉庫 | ||||||
| ○各地に国ができる | 青銅器(銅鐸・銅鏡・銅剣)・鉄器 | 上条遺跡(浜)に銅鐸が埋められる | ||||
| 57 | 倭の奴国王が漢に使いを送る→金印 | |||||
| 239 | 卑弥呼が魏に使いを送る | |||||
| 古墳 | ○古墳がつくられはじめる | 古墳・埴輪 | ||||
| ○倭国、朝鮮半島に出兵する | ||||||
| ○ヤマト王権による統一がすすむ | 周布古墳(前方後円墳)がつくられる(浜) | |||||
| ○倭軍、高句麗との戦いに敗れる | ||||||
| 大陸・半島の文化の伝来 | ||||||
| 漢字・儒教・技術 | 横穴式石室をもつめんぐろ古墳(円墳)がつくられる(浜) | |||||
| 須恵器の生産が盛んになる(日脚遺跡(浜)など) | ||||||
| 538 | (552年説もある)仏像・経典が百済から伝わる | 横穴式石室・横穴墓がさかんにつくられる(やつおもて古墳群(旭)など) | ||||
| 飛鳥 | 587 | 蘇我氏が物部氏をほろぼす | ||||
| 593 | 聖徳太子が摂政となる | |||||
| 604 | 十七条の憲法を定める | 法隆寺 | ||||
| 607 | 小野妹子を遣隋使として派遣する | 古墳築造の終末期(片山古墳(浜)) | ||||
| 630 | 遣唐使の派遣が始まる | |||||
| 645 | 大化の改新(はじめて年号を定める) | |||||
| 663 | 白村江の戦い | 薬師寺 | ||||
| 672 | 壬申の乱(大海人皇子) | 高松塚古墳壁画 | 寺院が建てられはじめる(重富廃寺跡(旭)、下府廃寺跡(浜)) | |||
| 701 | 大宝律令 | |||||
| 奈良 | 708 | 和同開珎がつくられる | 「古事記」(12) | |||
| 710 | 平城京に都を移す | 「日本書紀」(20) | 石見国府がつくられる(浜) | |||
| 741 | 国分寺・国分尼寺建立の詔 | |||||
| 743 | 墾田永年私財法 ○荘園のはじまり | 石見国分寺・国分尼寺が建てられる(浜) | ||||
| 東大寺大仏完成(52) | ||||||
| 鑑真の日本渡航(54) | ||||||
| 794 | 平安京に都を移す | 「万葉集」 | ||||
| 平安 | ||||||
| ○検非違使をおく | ||||||
| 天台宗(最澄) | ||||||
| 858 | 藤原良房が摂政となる | 真言宗(空海) | ||||
| 884 | 石見国司を那賀、邇摩の郡司らが襲う | |||||
| 887 | 藤原基経が関白となる | |||||
| 894 | 遣唐使を廃止する | 寝殿造 | ||||
| ○荘園が増えてくる | かな文字 | |||||
| 935 | 平将門の乱(~40) | 「古今和歌集」紀貫之(05) | ||||
| 939 | 藤原純友の乱(~41) | |||||
| ○武士のおこり | ||||||
| 1016 | 藤原道長が摂政となる | 「枕草子」清少納言 | ||||
| ○藤原氏が最も栄える | 「源氏物語」紫式部 | |||||
| 浄土信仰がさかんになる | ||||||
| 平等院鳳凰堂 | ||||||
| 1086 | 白河上皇が院政をはじめる | |||||
| 1167 | 平清盛が太政大臣となる | 中尊寺金色堂 | ||||
| 1180 | 源平合戦(~85) | 新しい仏教がおこる | ||||
| 浄土宗(法然) | ||||||
| 鎌倉 | 1192 | 源頼朝が征夷大将軍となる | 臨済宗(栄西) | |||
| 1205 | 北条義時が執権となる | 東大寺南大門金剛力士像(運慶・快慶) | ||||
| 1221 | 承久の乱 京都に六波羅探題設置 | 「新古今和歌集」 | ||||
| 1232 | 北条泰時が御成敗式目を定める | 浄土真宗(親鸞) | ||||
| 曹洞宗(道元) | ||||||
| 「平家物語」 | ||||||
| 1274 | 文永の役(元寇) | 日蓮宗(日蓮) | ||||
| 1281 | 弘安の役(元寇) | 1281 | 蒙古襲来に備え、石見海岸に18の砦が築かれたという | |||
| 1333 | 鎌倉幕府がほろびる | 「徒然草」吉田兼好 | ||||
| 室町 | 1334 | 後醍醐天皇による建武の新政 | ||||
| 南北朝 | 1336 | 南北朝の対立がはじまる | 三隅兼連(かねつら)率いる三隅氏(三)、周布氏(浜)、福屋氏(旭・金)、永安氏(弥)などが南朝方として、益田氏などの北朝方を相手に転戦する | |||
| 1338 | 足利尊氏が征夷大将軍となる | |||||
| ○倭寇がさかんになる | 1348 | 石見安国寺が定められる(浜) | ||||
| 1378 | 足利義満が室町に幕府を移す | 北山文化 | ||||
| 1392 | 南北朝が統一される | 金閣(足利義満) | ||||
| 1404 | 勘合貿易がはじまる | 能の大成(世阿弥) | ||||
| 1425 | 朝鮮国張乙夫ら10人が長浜に漂着し、周布氏と朝鮮との交易が始まる(浜) | |||||
| 1428 | 近畿地方で大きな土一揆がおこる | |||||
| 1429 | 尚氏が琉球を統一する | |||||
| ○各地で都市が発達する | 東山文化 | 1443 | 三隅信兼(三)の助力を得て宝福寺(浜)の大般若経が写経される(「浜田」の地名が記される現存最古の史料) | |||
| 戦国 | 1467 | 応仁の乱(~77) | 銀閣(足利義政) | 1467 | 三隅氏(三)などが使者を遣わして朝鮮と通交する | |
| ○国一揆・一向一揆が盛んになる | 書院造・水墨画 | 1471 | 朝鮮で編纂された「海東諸国記」に長浜、周布、三隅に関する記述がなされる | |||
| ○下克上がさかんに行われる | 庶民文化-お伽草子 | |||||
| 1543 | ポルトガル人が鉄砲を伝える | |||||
| 1549 | ザビエルがキリスト教を伝える | 南蛮文化 | 福屋氏(旭・金)が浜田方面に進出する | |||
| 「キリシタン版」(活版印刷) | 1561 | 中国で編纂された「籌海図編」などに石見国内の港として浜田・長浜などが記される(浜) | ||||
| 1562 | 福屋氏(旭・金)が滅ぶ | |||||
| 1570 | 三隅氏(三)が滅ぶ | |||||
| 安土・ 桃山 |
1573 | 織田信長が室町幕府をほろぼす | ||||
| ○太閤検地(82~) ○刀狩令(88) | 少年使節の出発(82) | 1582 | 吉川氏が伊甘郷(浜)をおさえる | |||
| 1590 | 豊臣秀吉が全国を統一する | 茶の湯の大成(千利休) | ||||
| 1592 | 豊臣秀吉の朝鮮出兵(~98) | 安土城・大阪城 | ||||
| 1600 | 関ヶ原の戦い | ふすま絵・屏風絵 | 1600 | 毛利氏の転封に従い、周布氏(浜)など石見の国人たちが長門国へ移る | ||
| 江戸 | 1603 | 徳川家康が征夷大将軍となり、江戸に幕府を開く | 阿国の歌舞伎踊りが流行する | 那賀郡は幕府直轄の石見銀山領となる | ||
| ○朱印船貿易がさかんになる | ||||||
| ○東南アジアに日本町が栄える | ||||||
| 1609 | 薩摩藩が琉球を征服する | |||||
| 1612 | 天領でキリスト教を禁止 | |||||
| 1615 | 豊臣氏がほろびる(大阪の陣) 武家諸法度の制定 |
1617 | 亀井氏が津和野に入って津和野藩が成立し、那賀郡の一部が津和野藩領となる | |||
| 日光東照宮 | 1619 | 古田氏が浜田に入って浜田藩が成立し、那賀郡の一部が浜田藩領となる | ||||
| 1623 | 浜田城と城下町がほぼ完成する | |||||
| 1635 | 日本人の海外渡航を禁止 参勤交代の制度を定める |
|||||
| 1637 | 島原・天草一揆(~38) | |||||
| 1639 | ポルトガル船の来航禁止 | |||||
| 1641 | オランダ商人を出島に移す | 朱子学の普及 | 1649 | 古田家断絶により、松平周防守家が浜田藩に転封となる | ||
| 1665 | 津和野藩が紙を専売制とする | |||||
| 1669 | 蝦夷地でシャクシャインの戦いがおこる | |||||
| ○農具の改良 新田開発が進む | 「日本永代蔵」井原西鶴 | |||||
| ○物流の発展 水運の発達 | 「奥の細道」松尾芭蕉 | 砂鉄採取、たたら製鉄が石見各地で行われはじめる | ||||
| ○商品作物の栽培がさかんになる | 浮世絵(菱川師宣) | 1696 | 津和野藩が紙をもって収納米にかえる(紙年貢) 紙製造がさかんに行われる |
|||
| 1709 | 新井白石の政治(~16) | |||||
| 1716 | 徳川吉宗の享保の改革(~45) | |||||
| 1722 | 上げ米の制 年貢の率の引き上げ | |||||
| 洋書輸入の禁止がゆるめられる(20) | ||||||
| 1732 | 享保の大ききん | 蘭学→鎖国の批判 | 1732 | 石見国でも大凶作、大ききんとなる 石見銀山領代官井戸平左衛門が甘藷(さつまいも)栽培をすすめる(翌年の死亡(1733)後、供養塔が石見各地で建てられる) |
||
| 1742 | 公事方御定書 | 「解体新書」前野良沢・杉田玄白ら | ||||
| 江戸 | 1759 | 松平周防守家にかわり、本多家が浜田藩に転封となる | ||||
| 1762 | 浜田城下で真宗寺院と他宗九か寺との間で宗教論争が起こる(浜) | |||||
| 1767 | 田沼意次の政治(~86) | 国学→尊王攘夷思想 | ||||
| 1769 | 本多家にかわり、松平周防守家が再び浜田に転封となる | |||||
| 1782 | 天明の大ききん(~87) | 1783 | 石見国でも大凶作、ききんとなる(~84) | |||
| ○百姓一揆・打ちこわしが増える | 「古事記伝」本居宣長 | |||||
| 1787 | 松平定信の寛政の改革(~93) | 庶民文化 | ||||
| 1792 | ロシアの使節ラクスマン、根室に来航 | 寺子屋の普及 | ||||
| 1806 | 伊能忠敬、石見から出雲へ海岸を測量 | |||||
| 赤瓦(石州瓦)の製造がさかんになる | ||||||
| 1808 | フェートン号事件 | 「東海道中膝栗毛」十返舎一九 | 1808 | 浜田藩医二宮彦可が著した日本最初の外科医書「正骨範」が発行される | ||
| 1812 | 浜田藩が紙漉奨励のため褒賞を出す | |||||
| 1817 | 浜田藩主が長浜人形の専売権を永見家に与える(浜) | |||||
| 1820 | 岡本甚左衛門が浜田藩の許可を得て七条原開墾に着手する(~29完成)(金) | |||||
| 1825 | 異国船打払令 | 「南総里見八犬伝」滝沢馬琴 | ||||
| 1833 | 天保の大ききん(~36) | 地図(伊能忠敬) | ||||
| 1836 | 松平周防守家にかわり、松平右近将監家が浜田に転封となる 今(会)津屋八右衛門らによる竹島事件(海外渡航)が発覚する |
|||||
| 1837 | 大塩平八郎の乱 | 川柳・狂歌 | ||||
| 1841 | 水野忠邦の天保の改革(~43) | 錦絵(葛飾北斎・歌川広重) | ||||
| 1853 | ペリーが浦賀に来航する | おかげまいりの流行 | ||||
| 1854 | 日米和親条約 | |||||
| 1858 | 日米修好通商条約 安政の大獄(~59) | |||||
| 1860 | 桜田門外の変 | |||||
| 1862 | 生麦事件→薩英戦争(63) | |||||
| 1864 | 四か国連合艦隊が下関を砲撃する | |||||
| 1866 | 第二次長州征伐 薩長同盟が結ばれる |
1866 | 第二次長州征伐の際、浜田藩など幕府軍は長州軍に破れ、浜田藩は自焼退城する 浜田藩領・石見銀山領は長州支配となる |
|||
| 1867 | 大政奉還 王政復古の大号令 | ええじゃなか運動 | ||||
| 明治 | ○明治維新 | 文明開化 | ||||
| 1868 | 鳥羽・伏見の戦い→戊辰戦争(~69) 五箇条の御誓文 五榜の掲示 |
東京・横浜間電信開通(69) | ||||
| 1869 | 旧幕府領・浜田藩領に大森県を置く | |||||
| 1869 | 版籍奉還 | 「横浜毎日新聞」(最初の日刊紙)創刊(70) | 1870 | 大森県庁を大森から浜田に移し、浜田県と改称する | ||
| 1871 | 郵便制度の制定 廃藩置県 日清修好条規「解放令」岩倉使節団出発 | 津田梅子ら女子留学生渡米(71) | 1871 | 津和野藩を廃し、浜田県に併合する | ||
| 1872 | 学制発布 新橋・横浜間に鉄道開通 | 太陽暦採用(72) | 1872 | 浜田地震 浜田県が郵便取扱所を開設する |
||
| 1873 | 徴兵令 地租改正 | 「学問のすすめ」福沢諭吉 | 1873 | 各地で「小学」(小学校)が開校し始める | ||
| 1874 | 民撰議院設立建白書 台湾出兵 | 1874 | 浜田県が県政に民意を反映させるため、民会(人民合同議事)を開設する 浜田県下で最初の新聞「浜田新聞誌」が創刊される(浜) |
|||
| 1876 | 日朝修好条規 | 1876 | 浜田県を廃し、島根県に併合する | |||
| 1877 | 西南戦争 | |||||
| 1881 | 国会開設の勅諭 自由党の結成 | 日本銀行(82) | ||||
| 1885 | 内閣制度ができる | |||||
| 1889 | 大日本帝国憲法の発布 | 東海道本線全通(89) | 1889 | 市町村制が施行される | ||
| 1890 | 教育勅語の発布 第一回帝国議会 | 北里柴三郎、破傷風血清療法を発見(90) | ||||
| 1894 | 領事裁判権の撤廃に成功(実効99~) 日清戦争(~95) |
「舞姫」森鴎外(90) | 1894 | 軍用の防寒用の紙布(しふ)として石州半紙の需要が急増(三) | ||
| 1895 | 下関条約→三国干渉 | 1895 | 浜田港が外国貿易港となる(浜) | |||
| 1898 | 歩兵第二十一連隊が広島から浜田に移る(浜) 能海寛が、チベット・ラサを目指し日本を出発する(金) |
|||||
| 1899 | 浜田港が開港場に指定される(浜) | |||||
| 1900 | 那賀郡の医師たちが世界で最初に種痘を行ったエドワード・ジェンナーの顕彰碑を建てる(浜) | |||||
| 1901 | 八幡製鉄所創業開始 | 1901 | 石見部で最初の図書館として私立図書館が開設される(浜) | |||
| ○産業革命が進む | ||||||
| 1902 | 日英同盟を結ぶ | |||||
| 1904 | 日露戦争(~05) | |||||
| 1905 | ポーツマス条約 | 「吾輩は猫である」夏目漱石(05) | 1907 | 皇太子(大正天皇)山陰各地を行啓 | ||
| 1910 | 韓国を併合する | 「破戒」島崎藤村(06) | 御便殿建設される(浜) | |||
| 1911 | 関税自主権を回復(条約改正の達成) | |||||
| 大正 | 1914 | 第一次世界大戦に参戦 | ||||
| 1915 | 中国に21か条の要求を出す | 「羅生門」芥川龍之介(15) | ||||
| 1917 | 島村抱月の芸術座が、劇中歌「カチューシャの唄」が大流行した「復活」を島根県下で公演する | |||||
| 1918 | 米騒動 シベリア出兵(~22) 原敬の政党内閣成立 | 吉野作造が民本主義を提唱(16) | 1918 | 浜田で米騒動、軍隊が出動する(浜) | ||
| 1920 | 常任理事国として国際連盟に加盟 | 1921 | 国有鉄道浜田線(出雲今市以西の路線)が浜田駅まで開通し、山陰本線に編入される | |||
| 1922 | 全国水平社結成 | 1922 | 山陰本線が三保三隅駅まで延伸される | |||
| 1923 | 関東大震災 | 1923 | 山陰本線が益田駅まで延伸される | |||
| 1925 | 治安維持法 男子普通選挙制の実現 | ラジオ放送の開始(25) | ||||
| 昭和 | ||||||
| 1931 | 満州事変おこる | 「伊豆の踊子」川端康成(26) | ||||
| 1932 | 満州国建国 五・一五事件 | 「蟹工船」小林多喜二(29) | ||||
| 1933 | 国際連盟を脱退する | |||||
| 1936 | 二・二六事件 | |||||
| 1937 | 日中戦争(~45) | |||||
| 1938 | 国家総動員法 | |||||
| 1940 | 日独伊三国同盟 大政翼賛会 | 1940 | 浜田町が市制を施行して浜田市となる | |||
| 1941 | 日ソ中立条約 太平洋戦争(~45) | |||||
| ○学童疎開(44~) 本土空襲(~45) | 1943 | 石見地方大水害 | ||||
| 1945 | 沖縄戦 広島・長崎に原子爆弾投下 ソ連の対日参戦 ポツダム宣言を受諾し降伏(第二次世界大戦終わる) |
|||||
| ○日本の民主化 | ||||||
| 1945 | 財閥解体 農地改革 女性に参政権が認められる 労働組合法 | |||||
| 1946 | 日本国憲法の公布→47施行 | 1946 | 冶金学者・俵國一が文化勲章を受章する(浜) | |||
| 1947 | 教育基本法 学校教育法 独占禁止法 労働基本法 | 6・3・3・4制の学制実施(47) | ||||
| 湯川秀樹、日本人初のノーベル賞受賞(49) | ||||||
| 1950 | 警察予備隊創設→54自衛隊 | |||||
| 1951 | サンフランシスコ平和条約(独立の回復)日米安全保障条約 | ユネスコ加入(51) | ||||
| テレビ放送の開始(53) | ||||||
| 1954 | 第五福竜丸が被爆 | |||||
| 1955 | 三隅町、岡見村、三保村、黒沢村、井野村と大麻村の一部が合併して、新・三隅町が発足する | |||||
| 1956 | ソ連と国交を回復、国際連合に加盟 | 原子炉に点火(57) | 1956 | 杵束村・安城村が合併して、弥栄村が成立する | ||
| ○高度経済成長はじまる | 1958 | 旭村が町制を施行して旭町となる | ||||
| 1960 | 日米安全保障条約の改定→安保闘争 | |||||
| 1963 | 豪雪災害 | |||||
| 1965 | 日韓基本条約 | 東海道新幹線開通(64) | ||||
| 1968 | 小笠原諸島の日本復帰 | 東京オリンピック(64) | 1969 | 金城村が町制を施行して金城町となる | ||
| 1972 | 沖縄の日本復帰 日中国交正常化 | 大阪万国博覧会(70) | ||||
| 1973 | 石油危機おこる | 札幌冬季オリンピック(72) | 1973 | 金城町民俗資料館が開館する(現・金城民俗資料館) | ||
| 1974 | 日本画家・橋本明治が文化勲章を受章する(浜) | |||||
| 1978 | 日中平和友好条約 | 沖縄海洋博(75) | 1978 | 金城町歴史民俗資料館が開館する(現・金城歴史民俗史料館) | ||
| 1979 | サミットが東京で開催 | 1979 | 三隅町歴史民俗資料館が開館する(現・三隅歴史民俗資料館) | |||
| 1981 | 旭町歴史民俗資料館が開館する(現・旭歴史民俗資料館) | |||||
| ○日米の貿易摩擦問題が大きくなる | 1982 | くにびき国体開催 | ||||
| 1983 | 集中豪雨による大災害 | |||||
| 1984 | 浜田市郷土資料館が開館する(現・浜田郷土資料館) | |||||
| 平成 | 1989 | 消費税が導入される | 日本人の宇宙飛行はじまる | 1989 | 中国横断自動車道広島浜田線浜田・旭間開通 | |
| 1991 | 湾岸戦争 | 秋山豊寛(90) 毛利衛(92) | 1991 | 中国横断自動車道広島浜田線全線開通 | ||
| 1995 | 阪神・淡路大震災 | |||||
| 長野冬季オリンピック(98) | 1998 | 中国電力三隅発電所1号機(火力)が営業運転を開始する | ||||
| 2000 | サミットが九州・沖縄で開催される | |||||
| 2004 | 新潟県中越地震 | |||||
| 愛知万博(05) | 2005 | 弥栄村郷土資料展示室が設置される 浜田市・金城町・旭町・弥栄村・三隅町の対等合併により、新・浜田市が発足する |
||||
| 2007 | 石見銀山 世界遺産登録 | |||||
| 2008 | 洞爺湖サミット開催 | 2008 | 島根旭社会復帰促進センター開庁 | |||
| 2009 | 衆院総選挙で民主党大勝 | 新型インフルエンザ | 2009 | 石州半紙 ユネスコ無形文化遺産に記載 | ||
| 2010 | 新浜田医療センター開院 浜田駅北地区整備事業完了 |
|||||
※ 浜田市のできごとのうち、主に各地域に関係するものについては下記のとおり注記している。
浜田地域…(浜)、金城地域…(金)、旭地域…(旭)、弥栄地域…(弥)、三隅地域…(三)
【平成22年11月18日 浜田市教育委員会文化振興課 作成】
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 教育部 文化振興課
-
-
電話番号:0855-25-9730
-