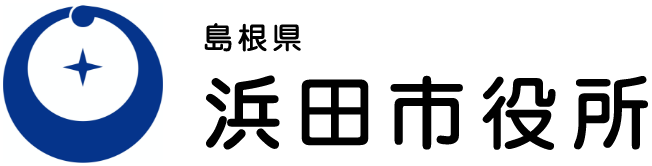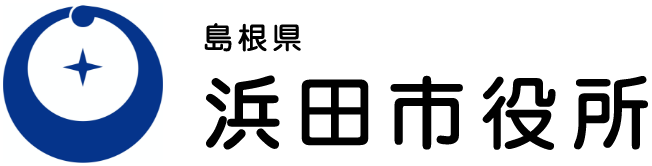1.はじめに
井野鉱山は太平洋戦争前後の昭和18(1943)年7月から昭和25(1950)年1月までの約7年間操業された鉱山です。
現在の三隅町井野徳泉寺集落に従業員やその家族が暮らす「小原町」と呼ばれた鉱山町、その東側丘陵に採掘場がありました。
今日では、鉱山町は水田や宅地に変わりましたが、採掘場跡は雑木や下草に覆われているものの、採掘跡のすり鉢状地形や鉄鉱石、トロッコのレール、鉱石運搬用空中索道のコンクリート製土台が確認できます。
2.井野鉱山成立の背景
昭和16(1941)年に太平洋戦争が勃発し、国内において鉄需要が高まりました。そのため、鉱物資源の分布に関する全国規模の地質調査が実施され、その調査をもとに全国各地で小規模鉄山が次々に開発されました。
こうした背景をもとに、井野鉱山は昭和18年7月から採掘事業が開始されました。また、井野鉱山の南に位置する黒沢鉱山においても昭和19年7月から採掘が開始されています。
3.井野鉱山における採掘事業
鉱区は徳泉寺集落東方の丘陵一帯に第1鉱床群から第7鉱床群まで設定されました。昭和20年には、鋼鉄輸送力を増強するため、三保三隅駅と井野鉱山を結ぶ全長約6キロに及ぶ空中索道が敷設されました。また、三保三隅駅には鉱石運搬専用の側線がつくられ、日本製鉄八幡製鉄所へ運搬されました。
4.井野鉱山の最盛期
昭和20(1945)年8月に太平洋戦争は終戦しますが、井野鉱山の採掘は続きました。そして、終戦間もなくから昭和21年にかけて、井野鉱山の出鉱量は開山以来最大となりました。昭和21年4月に発表された井野鉱業所の報告書には、前年度下期(10月~3月)の生産量は22,262トン、出鉱量18,172トンであり、昭和21年度の生産目標は7万トンと設定されています。昭和21年の全国の鉄鉱石産出量は55万トンで、井野鉱業所の出鉱量が生産目標通りの約7万トンだったと仮定すると、国内生産量の約13%を生産したことになります。井野鉱山の最盛期には、その山麓に従業員とその家族をあわせて約2千人が暮らしていました。
5.井野鉱山の終焉
昭和22(1947)年、井野鉱山の運営会社である鐘淵紡績会社は本来の繊維工業への回帰、また経営基盤の脆弱な繊維以外の部門を切り離すことを決めました。井野鉱山は廃止や売却は免れたものの、事業は縮小されました。そして、3年後の昭和25(1950)年1月に採掘を止め、鉱業所の建物、空中索道と関連設備の撤去が行われました。昭和27(1952)年には、井野鉱山の土地も地元の個人に売却され、以後、鉱山は再開されることなく今日に至っています。
6.井野鉱山の意義
太平洋戦争下の鉄需要の高まりにより井野鉱山は誕生しました。井野鉱山の盛衰を追うことにより、太平洋戦争下における紡績資本のコンツェルン化と軍事産業化のあり様を知ることができます。また、最盛期には国内生産量の約13%を占めるなど、近代工業の様相を知るうえでも重要な産業遺跡と言えます。
※上記は、神 英雄2012「太平洋戦争下の小規模鉄山に関する歴史地理学的考察-島根県浜田市三隅町の鐘紡井野鉱山の場合-」『島根地理学会誌』第46号 島根地学会 を要約したものです。
※なお、その後判明した事柄を付加して、神英雄『鐘紡井野鉱山史 戦後日本の復興を支えた鉱山の記録』(まちづくり推進委員会INO、2013』が刊行された。
詳しくは井野公民館までご連絡ください。




このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 教育部 文化振興課
-
-
電話番号:0855-25-9730
-