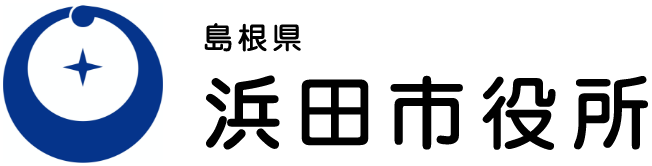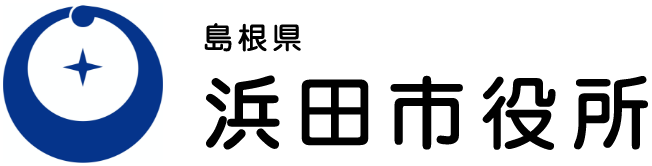児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
次に掲げる児童の母または父あるいは父母以外の養育者で、一定の要件等に該当する場合に支給されます。
児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の計算方法が変更されています。
児童扶養手当を受けることができる方
・次の条件に当てはまる児童を監護している母
・次の条件に当てはまる児童を監護し、かつ、これと生計をともにしている父
・父または母に代わってその児童を養育している方(養育者)
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が重度の障がい(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8 母が婚姻によらないで懐胎した児童
9 その他、上記に該当するか明らかでない児童
※児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているときも手当を受けることができません。
※申請する母または父が婚姻しているとき(事実上婚姻関係と同様にあるときを含む)は手当を受けることができません。
そのほか、詳しい支給要件についてはお問い合わせください。
手当の支給期間
手当は申請した月の翌月分から受給資格がなくなった月分までが支給対象となります。
児童の対象年齢は18歳に到達して最初の3月31日まで(心身に中度以上の障がいがある場合は20歳未満)です。
手当の額
| 区分 |
手当月額(令和7年4月分~) |
|
| 児童1人のとき | 第2子以降加算額 | |
| 全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
| 一部支給 |
46,680円~11,010円 |
11,020円~5,520円 |
<所得制限限度額>(令和6年11月分以降)
| 扶養親族の人数 | 受給資格者本人の所得 | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の所得 | |
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
|
3人 |
183万円 | 322万円 | 350万円 |
| 以降1人につき | 38万円加算 | 38万円加算 | 38万円加算 |
限度額に加算されるもの
1、受給者本人:老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者の限る)がある場合は1人につき15万円
2、扶養義務者等:老人扶養親族がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族等がすべて70才以上の場合は、1人を除く)
所得額の計算方法
所得額は、次の計算式により計算します。
所得額と上記の表を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかを決定します。
所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額ー80,000円(社会保険料相当額)ー下記の控除
<諸控除の額(主なもの)>
| 諸控除の内容 | 諸控除の額 |
| 寡婦控除 | 270,000円 |
| ひとり親控除 | 350,000円 |
| 障害者控除 | 270,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 配偶者特別控除・医療費控除など | 地方税法で控除された額 |
※手当を受けている方が母または父の場合は、寡婦控除とひとり親控除については、控除しません。
※地方税等における給与所得控除等の見直しに伴い、令和3年1月1日から児童扶養手当の支給を制限する場合の所得額の計算方法について、給与所得または公的年金等に係る所得を有する受給資格者の総所得金額の計算に当たり、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除することとされました。
なお、令和3年9月分以降の児童扶養手当の所得額の算定から適用されます。
手当の支給
手当は奇数月の10日に年6回、それぞれ前2か月分が支給されます。
(ただし、10日が金融機関の休業日にあたる場合はその直前の営業日です。)
※手当は、認定されると請求された月の翌月分から支給されます。
手続について
手続にあたっては家庭状況について詳しく確認する必要があるため、必ず受給者本人が来庁してください。
<請求に必要な添付書類>
|
支給要件 |
添付書類 |
|
|
共通 |
1 請求者及び対象児童の戸籍謄本または抄本 2 請求者及び対象児童の属する世帯全員の住民票の写し (注)続柄・本籍等の記載があるもの 3 公的年金調書(市町村で作成します) 4 養育費に関する申告書(請求者が父または母の場合) 5 個人番号の確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カード) 6 請求者の本人確認できる書類 (運転免許証、マイナンバーカードなど) その他:請求者の年金手帳・請求者名義の振込口座がわかるもの |
|
|
|
イ 離婚 |
事実婚解消の場合は事実婚解消に関する調書及び申立書 |
|
|
ロ 父または母 死亡 |
父または母死亡の記載のある戸籍謄本または抄本 |
|
ハ 父または母障害 |
障害認定診断書(障害基礎年金の1級に該当する場合は、年金証書の写) |
|
|
ニ 父または母生死不明 |
警察署、福祉事務所、その他官公署、関係会社等の証明書 |
|
|
ホ 遺棄 |
父または母が1年以上遺棄している事実を明らかにする遺棄 調書及び申立書 |
|
|
ヘ DV |
保護命令決定書の謄本 及び 確定証明書 |
|
|
ト 父または母拘禁 |
父または母が1年以上拘禁されている事実を明らかにする書類 |
|
| チ 未婚の父または母 | 事実婚解消等調書 | |
(注)これらの書類以外にも個別の事情により必要となる書類があります。
手続場所
市役所 子ども・子育て支援課11番窓口および各支所市民福祉課
手当を受けている人の届出
手当の受給中は次のような手続きが必要です。
|
現況届 |
受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。 提出がない場合は、手当の支給が停止されます。 また、2年間提出しない場合、時効により受給資格がなくなります。 |
|
額改定(増額)請求書 |
対象児童が増えたとき |
|
額改定届(減額) |
対象児童が減ったとき(対象児童が18歳になった場合は提出不要です。) |
|
資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき |
|
証書亡失届兼再発行請求書 |
手当証書をなくしたとき |
|
その他の届 |
氏名・住所・支払金融機関の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
◎届出が遅れたり、提出しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなかったり、場合によっては手当を返還していただくこともありますので、忘れずに提出してください。
◎上記のほか、受給資格の有無および額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。
ご注意!!
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず速やかに資格喪失届を提出してください。
届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになります。
1 手当を受けている母または父が婚姻したとき(内縁関係、同居、頻繁な定期的な訪問かつ金銭的援助がある場合等も同じです)
2 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます)
3 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(父または母からの送金や安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます)
4 拘禁されていた児童の父または母が出所したとき(仮出所も含みます)
5 受給者である母の児童が父と生計を同じくするようになったとき
6 受給者である父の児童が母と生計を同じくするようになったとき
7 その他受給条件に該当しなくなったとき
その他必要な手続
受給者や対象児童が市内で転居した場合「住所変更届」が、受給者や対象児童の氏名が変わった場合は「氏名変更届」が、手当の振込先を変更したい場合(申請者本人名義に限ります)は「口座振替支払申込書」が必要です。
また、新たに年金の受給を開始したとき、年金の子の加算が認定になったときなど、手当額の調整を行いますので、年金証書、通知書等をお持ちください。届出が遅れた場合には、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になることがあります。
手当の一部支給停止について
手当の受給開始から5年(所得超過による支給停止期間を含みます。)、手当の支給要件に該当した月から7年を経過したとき、または手当を請求した日に3歳未満のお子さんを監護している場合は、そのお子さんが3歳に達した翌月から5年を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止となります。
ただし、手当を受けている方が、次の適用除外事由のいずれかに該当する場合は、一部支給停止適用除外事由届出書と必要書類を提出していただくことで、従来どおり同額の手当を受給することができます。
| 適用除外事由 | 必要書類 |
| 雇用されているとき |
雇用証明書または健康保険証(社会保険証) |
| 就業しているとき | 自営業従事申告書 |
| 求職活動など自立を図るための活動を行っているとき | 求職活動等申告書・求職活動支援機関等証明書 |
| 採用選考を受け、就業活動を行っているとき | 求職活動等申告書または採用選考証明書 |
| 身体上または精神上に一定の障害があるとき |
障害年金等年金証書または身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し |
| 負傷または疾病により就業することが困難であるとき | 診断書または特定疾患医療受給者証の写し |
適用除外事由に該当する場合であっても、届出書の提出がないと、以降の手当額の2分の1が支給停止となりますので、ご注意ください。
対象となる方には、毎年6月中旬頃までに案内通知をご自宅に郵送しますので、その年の現況届とあわせて提出してください。
なお、対象となった年度以降も現況届を提出する際に届出書の提出が必要となります。
児童扶養手当と公的年金等の併給について
児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日以降は、公的年金給付等の額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分の手当が支給できるようになりました。
※詳しくはこちらをご覧ください。 こども家庭庁ホームページ
「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直しされました。
※詳しくはこちらをご覧ください。 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 子ども・子育て支援課
-
-
電話番号:0855-25-9331
-
- 金城支所市民福祉課
-
-
電話番号:0855-42-1235
-
- 旭支所市民福祉課
-
-
電話番号:0855-45-1435
-
- 弥栄支所市民福祉課
-
-
電話番号:0855-48-2656
-
- 三隅支所市民福祉課
-
-
電話番号:0855-32-2806
-