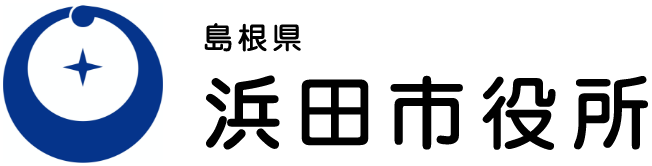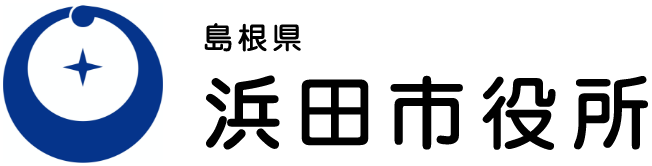この制度は、福祉医療対象者(重度心身障がい者及びひとり親家庭)に対して医療費(自己負担分)を助成することにより健康の保持と生活の安定を図ることを目的としています。
福祉医療を受けられる人
(1)65歳以上で引き続き3か月以上の寝たきりで他人の介護が必要な人(助成期間は1年限り)
(2)重度身体障がい者(身体障害者手帳1級又は2級を持っている人)
(3)重複重度障がい者(身体障害者手帳3級又は4級を持っている人でかつ概ねIQ50以下と診断された人)
(4)重度知的障がい者(療育手帳Aを持っている人)
(5)精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人
(6)精神障害者保健福祉手帳2級を持っている人で身体障害者手帳3級または4級を持っている人
(7)精神障害者保健福祉手帳2級を持っている人でかつ概ねIQ50以下と診断された人
(8)ひとり親家庭の人(18歳未満又は高校第3学年修了までの児童(20歳未満)を養育する配偶者のない者及び児童)
注:健康保険未加入者は対象となりません。
注:(1)~(7)の20歳以上の人は所得制限(特別障害者手当の所得額を準用)があります。
(この所得額には障害年金などの非課税収入も含んで審査します。)
注:(8)は前年分の所得税が非課税の世帯が対象となります。
重度心身障がい者の所得制限限度額表
受給資格者本人
| 扶養親族数 | 所得額 |
| 0人 | 3,661,000 円 |
| 1人 | 4,041,000 円 |
| 2人 | 4,421,000 円 |
| 3人 | 4,801,000 円 |
| 4人 | 5,181,000 円 |
| 5人 | 5,561,000 円 |
・扶養親族等のうち特定扶養親族がある場合は、上記の限度額に、特定扶養親族1 人につき25 万円を加算します。
・扶養親族等が7 人以上の場合の限度額は、588 万4 千円に1 人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者及び老人扶養親族であるときは、1 人につき10 万円、特定扶養親族であるときには、1 人につき25 万円を更に加算)を加算した額とします。
※判定所得額から各種控除を行った額で審査します。
自己負担額
- 対象者の自己負担割合は、「医療費の1割」です。
- 薬局など(注1)では、自己負担はありません。
- 1か月、1医療機関当たり(医科、歯科別)の自己負担額は、次の金額を上限とします。
| 区分 | 入院 | 外来 |
|---|---|---|
|
市町村民税課税世帯の方
|
20,000円
|
6,000円
|
|
市町村民税非課税世帯の方
|
2,000円
|
1,000円
|
|
20歳未満の障がい児(者)
|
2,000円
|
1,000円
|
- 医療機関などで、1割を超える、又は自己負担限度額を超える医療費を負担した場合は、助成申請により医療費の払い戻しをします。
- 助成対象は、健康保険が適用される医療費に限ります。(予防接種代、薬の容器代、入院時の食事代・差額室料、検診代、文書料など保険診療でない医療費や大きな病院に紹介状なしでかかった際の選定療養費は助成対象外です。)
(注1)薬局などとは、調剤薬局(院外)、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用補装具製作所、訪問看護ステーションのことです。
有効期間について
各種手続
- 住所や氏名が変わったとき、健康保険の種類や記載事項が変わったとき(福祉医療資格内容変更届(自署での署名または押印)、健康保険の変更の場合は資格情報のお知らせまたは資格確認書)
- 紛失などにより医療証の再交付を受けるとき
- 転出や死亡、ひとり親家庭の親又は子の婚姻などにより、資格を失ったとき
- 交通事故に遭ったとき
※代理の方が手続きをされる場合は、委任状と代理の方の本人確認ができるもの(運転免許証など)が必要となります。
医療機関のかかり方
払い戻し手続について
払い戻しを受ける場合
(1)医療機関などで、1割を超える自己負担割合で医療費を負担したとき
(2)医療機関などで、自己負担限度額を超える医療費を負担したとき
(3)マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)または資格確認書を忘れるなどで、医療機関に提示できず、医療費の全額を支払ったとき(まずご自身が加入されている健康保険に対して保険給付分の申請をしてください)
(4)コルセットなどの治療材料の給付を受けたとき( 一旦全額負担となりますので、まずご自身が加入されている健康保険に対して保険給付分の申請をしてください)
払い戻しの手続に必要なもの
(1)領収書(受診者氏名、保険診療点数が記載されているもの)
(3)福祉医療証又は資格証
(4)診断書兼装具装着証明書(治療装具の購入の場合のみ)
(5)健康保険の支給決定通知書(医療費を全額支払った場合や高額療養費の支給対象となった場合)
注:(5)については健康保険から医療費の支給がある場合には必ず提出してください。
※郵送で手続きをされる場合は、上記必要なものと福祉医療費助成申請書(1か月、1医療機関(医科、歯科別)ごとに必要・自署での署名または押印)を提出してください。
限度額適用認定について
入院等で医療費が高額となる場合は、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用する方は、医療機関に設置しているカード読み取り機で限度額情報の提供に同意して受診してください。マイナ保険証を利用しない方は、ご加入の保険者から「限度額適用認定証」または「限度額情報が併記された資格確認書」の交付を受けて医療証(資格証)と一緒に医療機関へ提示してください。
(限度額適用認定証の交付手続きにつきましては、各保険者へご確認ください。)
「子ども医療費受給資格証」をお持ちの方へ
高校生年代(注)では、「福祉医療費医療証」(ピンク色)を優先してください。
福祉医療費医療証をお持ちの方で未就学児・小学生・中学生の方は、「子ども医療費受給資格証」のみ提示して受診してください。
高校生年代(注)の方は、福祉医療を優先(子ども医療を併用)します。「福祉医療費医療証」と併せて医療機関等の窓口に提示してください。福祉医療と子ども医療の自己負担額が同一の場合は福祉医療のみを使用してください。
(注)高校生年代とは、15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までのことです。
独自利用事務について
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外にマイナンバーを独自に利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2項に基づき条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等の情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)
福祉医費助成制度は、国の承認により情報連携を行います。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第9号及び個人保護情報保護委員会規則に基づく届出)、承認されています。
| 執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
| 市長 | 1 | 浜田市福祉医療費助成条例(平成17年条例第124号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
| 市長 | 2 | 浜田市福祉医療費助成条例(平成17年条例第124号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
| 市長 | 5 | 浜田市福祉医療費助成条例(平成17年条例第124号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
根拠規範(浜田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例)
根拠規範(浜田市福祉医療費助成条例・福祉医療費助成条例施行規則)
届出1 届出書
届出2 届出書
届出5 届出書
サイト内の関連リンク情報
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 医療保険課
-
-
電話番号:0855-25-9411
- メールアドレス:hoken@city.hamada.lg.jp
-
- 金城支所 市民福祉課
-
-
電話番号:0855-42-1235
-
- 旭支所 市民福祉課
-
-
電話番号:0855-45-1434
-
- 弥栄支所 市民福祉課
-
-
電話番号:0855-48-2656
-
- 三隅支所 市民福祉課
-
-
電話番号:0855-32-2807
-