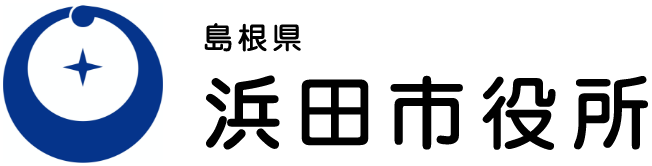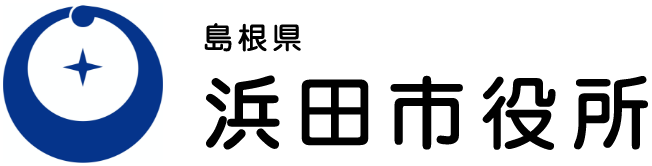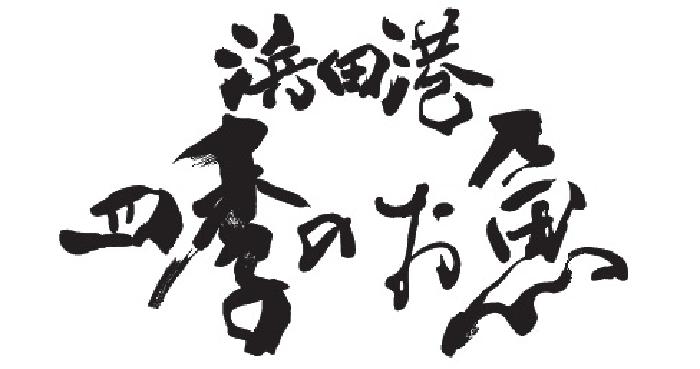
 「山陰浜田港」は、県内随一の水揚げを誇る漁港で、毎日数多くの魚が水揚げされ、全国各地へ出荷されています。
「山陰浜田港」は、県内随一の水揚げを誇る漁港で、毎日数多くの魚が水揚げされ、全国各地へ出荷されています。
島根県西部沖は、暖かい対馬暖流と島根冷水域といわれる深海の冷たく栄養に富んだ海水とが混ざり合い、魚の餌となるプランクトンの発生量も多い海域です。こうした自然条件が豊かな漁場を作り、おいしい魚を育てています。
この魚(貝類・藻類含む)の代表を、旬の季節ごとに数種ずつピックアップしたもの
・・・それが、「浜田港四季のお魚」です。
春[3月・4月・5月]の魚 13魚種
夏[6月・7月・8月]の魚 10魚種
秋[9月・10月・11月]の魚 16魚種
冬[12月・1月・2月]の魚 21魚種
| No | 名前 | 写真 | 説明文 |
| 1 |
アカアマダイ (秋・冬) |

|
アカアマダイは水深約60~100mに生息していて、底びき網、はえ縄で主に漁獲されます。アマダイという名前は、身に上品な甘さがあることや、横顔が頬被りをした尼僧に似ていることに由来します。 |
| 2 |
アカカマス (春・冬) |

|
アカカマスは全長30~50cmの細長くスマートな白身魚です。旬の時期には脂がのり、身が柔らかくなるため、刺身や塩焼きなどで美味しく楽しめます。干物や練り製品としても人気があり、多様な調理法で親しまれています。透明感のある身と澄んだきれいな目をしているものが新鮮で、体表にぬめりがあるものは脂があると言われています。 |
| 3 |
アカナマコ (冬) |

|
ナマコ類はウニやヒトデと同じ棘皮動物に属する海洋生物です。島根県で漁獲されるナマコは、マナマコ(アオナマコ・クロナマコ)とアカナマコがあります。赤褐色の斑紋が特徴的な「アカナマコ」は、他のナマコに比べ高価で、漁獲対象として多く採られます。 コリコリとした独特の食感と風味は一度食べるとクセになる味わいで、酢の物として親しまれています。また茶ぶりなまこ(切ったナマコをお茶で煮たもの)は臭みが取れ、食感が柔らかくなり生とは違った食感が味わえます。 |
| 4 |
アナゴ (春・秋・冬) |
|
山陰浜田港のアナゴは、東京湾や瀬戸内海のものより大型なのが特徴で、肉厚で脂の乗りが良いです。 |
| 5 |
アワビ (夏・冬) |

|
アワビは殻が一枚からなる巻き貝で、巻き貝の中でも最も美味な高級食材です。島根県には、メガイアワビ、クロアワビ、マダカアワビが生息しています。秋から冬にかけて産卵するアワビは夏が旬であり、刺身はもちろん、酒蒸し、バター焼きなどにして食べます。 アワビは殻の大きさが10cm以上の漁獲サイズになるのに4年もかかります。 |
| 6 |
アンコウ (秋・冬) |

|
山陰浜田港のアンコウ水揚量は全国でも上位に入り、味もトップクラスです。冬に鍋として食されることが多い魚です。 体全体がやわらかいので、まな板ではさばきにくく、下あごを鉤に引っ掛けて吊るし切りにします。この吊るし切りはアンコウ独特のさばき方です。「アンコウの七つ道具」という言葉が有名なように、アンコウは捨てるところがない魚といわれており、鍋以外に身は唐揚げ、皮は酢の物、肝は酒蒸し、肝ステーキなど多くの調理法があります。 |
| 7 |
イサキ |

|
イサキは、夏になると脂がのってくる魚で、磯釣りの魚としても人気のある大衆魚です。磯の香りを纏ったあっさりとした上品な味わいが特徴的で、刺身、塩焼き、ムニエルなど、多彩な調理法で楽しめる魚です。皮が厚いため塩焼きにすると、皮の旨みが非常に強く出ておいしく味わえます。 |
| 8 |
ウスバハギ (秋・冬) |

|
ウスバハギは、秋から冬にかけてが旬の魚で最大で70㎝近くまで成長します。特徴的な四角い体型と全体的に灰色で目立った斑紋はありませんが、若い個体には斑紋がある場合もあります。 身は淡白でクセがなく、熱を通しても硬くならないため、刺身だけでなく、揚げ物、鍋物にも向いています。旬の時期には、豊富な肝を生かした料理がおすすめです。 |
| 9 |
ウチワエビ (春・冬) |

|
全国的に漁獲量はそれほど多くなく、希少価値の高いエビです。甘みがあり、味は伊勢エビにも負けません。活けなら刺身も美味ですが、めったに食べられない貴重なものです。一般的にゆでる、焼く、天ぷら、フライなどにして食べます。 産卵期は秋で、卵はメスが腹に抱えて保護し、ふ化したら海を漂いながら成長し、海底に棲みつきます。 |
| 10 |
カジメ (春) |
画像準備中 |
海藻はアルギン酸などの食物繊維をはじめ、カルシウムなどのミネラルやビタミン類が豊富です。 カジメは多年生藻で、細く刻んで味噌汁に入れると一瞬で鮮やかな緑色に変わり、ネバネバ・トロトロになります。 |
| 11 |
カレイ (秋・冬) |

|
浜田市のカレイ塩干加工の生産量は、全国で上位を占めています。山陰浜田港で獲れる主なカレイは、「ミズカレイ(ムシカレイ)」「エテカレイ(ソウハチ)」「ササカレイ(ヤナギムシカレイ)」です。カレイは塩干しすることにより、上品な旨みが引き立ち、特に浜田名産の「一夜干し」は脂もよく乗り絶品です。 鮮度落ちの早い魚ですが、ミズカレイの刺身を提供できる取り組みを進めています。 8月~翌年2月に漁獲され、サイズが50g以上のものを「どんちっちカレイ」(ミズカレイ・エテカレイ・ササカレイ)としてブランド化しています。 |
| 12 |
ケンサキイカ (春・夏・秋・冬) |

|
浜田市では、マイカ・白イカとも呼びます。マイカという呼び名はややこしく、その土地によってケンサキイカのことだったり、スルメイカのことだったりします。その地方でたくさん獲れ、家庭でよく食べられるイカをマイカという傾向があります。 |
| 13 |
サザエ (夏・秋) |

|
サザエの産卵期は夏で、この頃に生殖巣が発達します。いわゆるしっぽの部分ですが、これが緑色であればメスで、クリーム色であればオスです。産卵後ふ化したものは海藻の中で成長し、殻の高さは1年で1cm、2年で3cm、約3年で漁獲サイズの6cmに達します。 サザエは棘のあるものとないものがありますが、これは生息場所の違いによります。波の荒い磯では棘が発達し、波の静かなところでは棘のないものが多いです。 |
| 14 |
サワラ (秋・冬) |

|
サワラは、もともと太平洋や瀬戸内海などの暖海の魚として知られていましたが、近年日本海における漁獲量も増えており、山陰浜田港ではまき網などで漁獲されるようになりました。照り焼きなど加熱調理向けのイメージが強い魚ですが、大型のものは刺身も美味です。 |
| 15 |
シイラ (夏・秋) |

|
シイラは海の上層部を群れをなして泳ぎます。そして、流れ藻や流木などの漂流物の陰に集まる習性があり、その性質を利用したユニークな漁法に「しいら漬け」があります。 白身でくせがなく、刺身、塩焼き、照り焼き、フライなどの料理に使われます。また島根県ではシイラを酢で締めた沖づくりと呼ばれる漁師料理がポピュラーです。 |
| 16 |
スルメイカ (冬) |

|
島根県ではスルメイカをサルイカ・シマメイカとも呼びます。他のイカ類と同様に寿命は約1年で、秋から冬に山陰沖から東シナ海にかけての海域で生まれ、春から夏にかけて北上し、秋から冬にかけて産卵のために再び南下します。 刺身、フライ、炒め物など和洋中さまざまな料理に利用され、スルメ、塩辛などの加工食品も多く、昔からなじみの深い食材です。 |
| 17 |
タチウオ (冬) |

|
タチウオは、太刀に似た姿から「太刀魚」の名が付けられたとも、立って泳ぐ姿から「立ち魚」の名が付けられたともいわれる魚です。 全国的にみても有名な魚ですが、山陰浜田港では主に沖合底びき網で漁獲されます。底びき網による漁獲のため、やや色が白っぽいのが難点ですが、脂の乗りが良く、美味しい魚です。 |
| 18 |
トビウオ (夏) |

|
華やかな夏を告げる魚として馴染みが深いこと、島根県の生産量が全国屈指であること、空中を飛ぶ様子が飛躍・跳躍のイメージがあることなどの理由で、島根県の魚に選定されています。 トビウオの身は脂肪やエキス成分の少ないやや淡白な味で、刺身、たたき、塩焼き、つみれ汁、薩摩揚げなどにして食べられます。また、卵巣も珍味で、煮付けなどにされます。加工品としては練製品、干物、くん製品などがあります。 |
| 19 |
ノドグロ(アカムツ) (春・夏・秋・冬) |

|
浜田市の魚に制定されています。 口の中が黒いことから「ノドグロ」と呼ばれています。島根県では小型のものをメッキンと呼んでいます。脂の乗りはトロにも匹敵するといわれ、身は柔らかく淡い紅色をしています。 山陰浜田港は日本有数の水揚港であり、8月から5月に扱われる、サイズが80g以上の高鮮度のものを「どんちっちノドグロ」としてブランド化しています。 煮付け、焼きが一般的ですが、極めつけは刺身、特にカツオのタタキのように皮の部分をあぶった刺身は最高です。またにぎり寿司、開いて干物にされます。 |
| 20 |
バトウ(マトウダイ) (秋・冬) |

|
島根県では「バトウ」と呼ばれるマトウダイは、漢字で書くと「的鯛」、「馬頭鯛」となり、体の真ん中に弓の的のような黒班があること、顔が馬の頭に似ていることが名前の由来になっています。 バトウのエサの食べ方は特徴的で、口を大きく開けて前方に長く伸ばし、海中のエサを吸い込むようにして食べます。 刺身、煮付け、フライなど、いろいろな料理に使える便利な魚です。 |
| 21 |
ヒラマサ (夏・秋) |

|
ヒラマサは、ブリに酷似しながらも、より温暖な海域を好む魚で、その旬は夏にあたります。成長すると全長約1.5m、体重50kgに達することもありますが、最もおいしいとされるのは2〜3kg程度の脂がほどよくのった個体で、この大きさが刺身や寿司ネタとしてよく使われます。 ブリよりやや細身で頭が小さく、体の黄色い線が真ちゅう色に近い濃い黄色であるのが特徴です。 |
| 22 |
ブリ (秋・冬) |

|
出世魚として有名なブリは、成長するにつれて呼び名が変わります。その呼び名も地域で異なりますが、島根県では、モジャコ、ツバス、ワカナ、ハマチ、メジ、マルゴ、ブリと呼び名が変わっていきます。 寒い時期に旬を迎えるブリ(寒ブリ)は刺身、照り焼き、煮付け、しゃぶしゃぶなど様々な料理で楽しむことができます。 |
| 23 |
ホウボウ (夏・秋・冬) |

|
ホウボウは、鮮やかな青緑色の胸びれを広げ、脚のように変化した胸びれで海底を歩く独特の生態を持つ魚です。その淡白で締まった身は、高級白身魚として知られ、タイに匹敵する美味しさを誇ります。刺身や煮付けはもちろんですが、アラから出汁がよく出るので鍋や汁物もおいしいです。 |
| 24 |
マアジ (春・夏・秋) |

|
山陰浜田港に水揚げされるマアジは他産地のものより脂ののりが良く、脂質含有量が旬には10%を超え、時には15%を超えることが島根県水産技術センターの調査で明らかになっています。そこで概ね4月から9月の旬の時期に50g以上のマアジを「どんちっちアジ」としてブランド化しました。 脂がのっているため刺身は旨味があり、 開き干しは焼くとふっくらとして奥深い味を生み出します。 |
| 25 |
マサバ (春・冬) |

|
日本近海にいるサバはマサバとゴマサバの2種類で、島根県で水揚げされるサバのほとんどがマサバです。マサバは背中に唐草模様のような模様があり、腹部には模様はなく、体はやや平たいです。 山陰浜田港に水揚げされるマサバは、一般的な旬の秋から冬だけでなく春にも脂がのります。サバをすき焼きのようにして食べるサバの煮食いは浜田市の郷土料理で、いりやきとも呼ばれています。 |
| 26 |
マダイ (春・冬) |

|
日本では昔から高級魚として珍重され、祝い事には欠かせない魚です。春先のマダイは産卵期にあたり、「桜鯛」と呼ばれ、脂が乗って大変美味しくなります。 刺身や塩焼き、ちり、頭の煮物、潮汁などといった料理に使われ、捨てるところがありません。 |
| 27 |
マフグ (春・冬) |

|
マフグの体表はとげがなくなめらかで、尾びれは黄色っぽいです。だしがよく出るので、鍋料理にして食されます。島根県にはフグを使った数多くの加工品が生産されています。その一つに「フグ味醂干し」があり、 浜田の名産品となっています。 |
| 28 |
レンコダイ(キダイ) (春・秋・冬) |

|
マダイに似ていますが、その名のとおり体の色が黄色味の強い赤色をしていることや、体表に青い斑点がないことで見分けることができます。鮮度が良いものほど口や目のまわりなどの黄色が濃いです。 レンコダイは成長の過程で性転換する魚で、1~2歳くらいまではメスの割合が高いですが、その後メスからオスへと性転換を行い、5歳以上ではオスの割合が高くなります。 |
| 29 |
ワカメ (春) |
画像準備中 |
ワカメは1年生藻です。 ワカメは生長すると茎の左右にひだができ始め、これが大きくなると、いわゆる「芽カブ」になります。芽カブはワカメの子どもをつくる部分で、春から初夏に成熟し、そこからとても小さい遊走子が、たくさん海中に泳ぎだして岩などに付着し、糸状の固まり(配偶体)になります。そして、秋になると配偶体から発芽して、ワカメに成長します。 ワカメは、ビタミン類、ミネラル、食物繊維が豊富であり、栄養価に非常に優れた海藻です。 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 水産振興課
-
-
電話番号:0855-25-9520
-