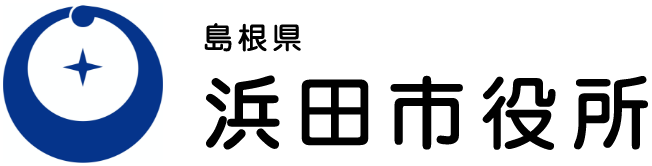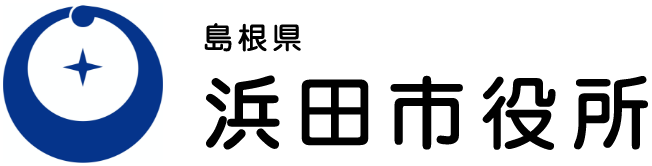| 会議名 | 第4回石見神楽伝承内容検討専門委員会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | 令和6年8月27日(火) 18時30分~20時25分 | |||
| 開催場所 | 浜田市立中央図書館2階 多目的ホール | |||
| 会議の担当課 | 文化振興課神楽文化伝承室 | |||
| 議題 |
1.報告事項 石見神楽伝承内容検討専門委員会の中間とりまとめ結果について 2.協議事項 石見神楽の情報発信に関する検討について |
|||
| 議事録 | 第4回石見神楽伝承内容検討専門委員会議事録(PDF/560KB) | |||
|
オンラインでの 公開・非公開 |
公開(会議の動画はこちら) | |||
配布資料
資料1_石見神楽伝承内容検討専門委員会の中間とりまとめ結果について(PDF/413KB)
資料2_石見神楽の情報発信に関する検討について(PDF/94KB)
浜田市議会石見神楽振興議員連盟からの意見について(PDF/326KB)
主な意見
グループワーク意見(石見神楽の情報発信に関する検討について)
Aグループ(豊田委員、小川委員、梅津委員、植田委員、真島委員)
|
情報発信する内容 |
手法 |
|
・石見神楽に求められているニーズを見極めた情報 ・興味を持っている人向けの詳細な情報 ・石見神楽の原点 ・調査研究した正しい石見神楽の知識 ・保存・伝承に向けて切羽詰まっている状況(現在、専門委員会を開いて検討を行っているような状況であること) |
【PR】 ・ホームページやSNSの充実(インバウンド対応含む) ・全国規模の神楽大会や校定石見神楽台本に掲載されている演目全てを演じる大会の開催
【体験・学習機会の創出】 ・石見神楽の舞と歴史を一緒に学ぶことが大切
【拠点施設】 ・石見神楽に係る古い物の収蔵や展示をする場は必要 ・施設においては、石見神楽の研究者やガイドなどが必要 ・神楽について学べる拠点施設で、舞(舞殿)を外すことはあり得ない。そこに行けば浜田の石見神楽が全てわかる場所にすべき
【調査研究】 ・石見神楽の正しい知識を説明できる人が必要 ・石見神楽が行われている範囲を明らかにする ・石見神楽の歴史(どのように伝わったか、どのように変化してきたかなど)を整理し、発信する ・発掘されていない遺産、書物の調査 ・他の神楽と比較して石見神楽の特異性を明らかにする
【その他】 ・社中の団員にも保存継承の意識を持ってもらうことも大切 ・公演の回数や場所がありすぎて価値が下がっている。一方でこれが世間のニーズでもある ・夜明け舞を受け入れられない地域が多くなっている ・飲食(特にお酒)と一緒に神楽を楽しめると良い ・石見神楽の魅力を伝え、案内できる人(ガイド)が必要 ・高千穂は、神楽の観方も発信している |
Bグループ(浅沼委員、山本委員、丸山委員、柿田委員)
|
情報発信する内容 |
手法 |
|
・石見神楽の特徴・歴史 ・浜田が石見神楽を創り出したまちということ ・海外旅行者に対する広島からのアクセスの良さ
|
【PR】 ・海外旅行者に向けたPR →広島からのアクセス方法、英語検索に対応したホームページなど(併せて受け入れ体制を整備することも必要) ・石見神楽のアニメ制作 ・舞を紹介する動画の制作 ・神楽大会などにおいてイヤホンガイドなどにより上演中に演目の解説を行う ・市内事業所など各所で浜田市が神楽のまちであることをPRする
【体験・学習機会の創出】 ・子どもが石見神楽を観る機会を増やす →小学校への出前神楽の実施、出前神楽に対する支援 ・高校生など若者が子どもに神楽を見せ、あこがれにつなげる ・石見神楽の特徴や歴史、六調子と八調子の違いなどが分かりやすい図書の作成
【拠点施設】 ・施設を整備するのであれば、多目的ホールではなく、石見神楽に特化したものであるべき。特に舞殿は本物の舞(夜明け舞など)が観ることができる音響や照明、防音設備を備えた専用施設で、3方4方から見ることができる環境が良い
【その他】 ・石見神楽の面、衣裳などを活用するためには、良い状態に保つ必要があり、市が管理・保存を行う ・石見神楽ファン以外の市民の方の理解も必要 |
Cグループ(大賀委員、川神委員、小林委員、福浜委員)
|
情報発信する内容 |
手法 |
|
・社中の活動内容や入り方など ・浜田が石見神楽を創り出したまちということ ・解説付きの演目の映像 ・神楽関係者の想い ・夜神楽に関する情報(各社中に確認が必要)
|
【PR】 ・石見神楽を創り出したまち浜田の根拠を明確にして発信する ・求められる情報が何か、改めて掲載情報の検討や、ニーズ調査が必要 →市民の石見神楽に係る情報源を調査 →入門編と上級者編など情報にグラデーションをつけることが必要 ・歌舞伎など認知度の高い伝統芸能を参考とする ・市民が口コミで魅力を発信できるよう、市民が石見神楽について知ることが必要 ・情報を取りまとめる窓口や組織が必要 ・石見神楽に関する映像制作 →石見神楽の制作過程、関係者の想い、演目の解説、VR映像、アニメなど ・SNSの活用 ・神楽関連商品開発コンテストやフォトコンテストの開催(市民の関わりしろを作る) ・宿泊施設等で衣裳・面・蛇胴等の展示 ・アクアスなど観光客が訪れる場での公演 ・情報発信については商標登録等権利関係の状況に留意する必要がある
【体験・学習機会の創出】 ・子どもの時から切れ目なく触れる機会の創出 ・保育園での活動など、実際に体験することが効果的 ・ボランティア・平日の活動など、社中ごとの努力で継続させていくことは限界があるため、支援が必要 ・ジオラマ作りなど、夏休みの自由研究と結び付ける
【その他】 ・休日(石見神楽の日)を制定する ・2025 大阪・関西万博での石見神楽公演は浜田市への誘致のためのチャンスである ・映像制作については島根県へ協力を仰ぐべき ・情報発信を社中で担うのは難しい。PRが上手な人に依頼すべき ・観光客の誘致には、地域との連携が不可欠 ・地域の行事として市民の理解を得るため、社中と地域との連携が必要 ・市民に自分たちの住む地域への関心(祭礼、行事など)をもってもらうことが大切 ・消滅の危機にある社中のフォローが必要 |
問い合わせ先
浜田市殿町1番地
浜田市教育部文化振興課神楽文化伝承室
電話 0855-25-6301
e-mail bunka@city.hamada.lg.jp
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 教育部 文化振興課
-
-
電話番号:0855-25-9730
-