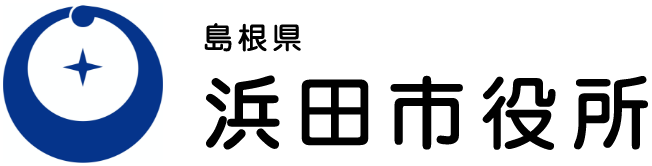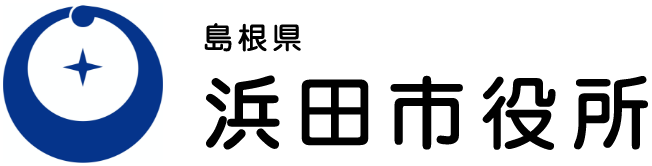特定外来生物とは
もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生き物のことを「外来生物」といいます。
「特定外来生物」とは、外来生物の中でも特に生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を与える、または、与えるおそれがあるものとして「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」により指定されているもので、飼育、栽培、保管、運搬などが禁止されています。
令和6年7月1日現在162種類が「特定外来生物」に指定されています。
島根県で見られる特定外来生物
2023年3月 島根県自然環境課発行「しまねの外来種ガイド」において、「島根県で見られる陸の外来種たち」「島根県で見られる水辺の外来種たち」として掲載されている中から、特定外来種を抜粋して掲載しています。
なお、写真及び説明は「しまねの外来種ガイド」に掲載されているものとは異なります。
写真出典:環境省ホームページ https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html
陸の特定外来生物
■ アライグマ
 鼻から眉間にかけて黒い線と、目の周りに黒い帯
鼻から眉間にかけて黒い線と、目の周りに黒い帯
ひげは白色
尻尾はこん棒状 5~7本程度の黒い縞あり
■ セアカゴケグモ
 成熟したメスの体長は約1cm
成熟したメスの体長は約1cm
全体が光沢のある黒色で、腹部の背面にはひし形を並べたような赤い線あるいは直線状の赤い線あり
港湾地域またはそれに隣接する地域で多く発見
生息場所は、地面や人工物のくぼみ、穴、裏側及び隙間など
攻撃性はないが、触ると咬まれることあり
※ 強い毒性を持っているため、見つけたら絶対に手で触れないようにしてください。
※ 駆除する際には、殺虫剤を使う、熱湯をかける、靴で踏みつぶすなど素肌に触れない方法を用いてください。
■ ソウシチョウ
 全長15cm程度 スズメ大の大きさ
全長15cm程度 スズメ大の大きさ
体色は暗緑色で眉斑から頬は薄い黄色
のどは黄色で胸は濃いオレンジ色
翼に黄色と濃い赤の斑紋
くちばしは赤色
「キョローンキョローン」と大きな声で鳴く
■ アレチウリ

 ウリ科の1年草
ウリ科の1年草
葉はザラザラしている
粗い毛を密生したつるを伸ばし群生することが多い
夏から秋に直径1㎝程度の黄白色の花が集まって咲き、鋭い棘を密生した果実をつける
※ 駆除する際には根から抜き、天日にさらし枯らしてから、ごみとして処分してください。
■ オオキンケイギク
 5月~7月にかけて、直径5~7㎝の黄橙色の花を咲かせる
5月~7月にかけて、直径5~7㎝の黄橙色の花を咲かせる
葉は細長いへら状
※ 駆除する際には根から抜き、天日にさらし枯らしてから、ごみとして処分してください。
水辺の特定外来生物
■ アカカミガメ
 頭の横に赤い模様
頭の横に赤い模様
子ガメは全身が緑色で甲羅は丸い
※2023年6月1日に「条件付特定外来生物」に指定されました。
一般家庭でペットとして飼うこと等は可能ですが、野外に放すこと等は禁止されています。
最後まで責任をもって飼いましょう。
■ アメリカザリガニ
 オスはハサミ足が大きく、全身が赤くなる
オスはハサミ足が大きく、全身が赤くなる
※2023年6月1日に「条件付特定外来生物」に指定されました。
一般家庭でペットとして飼うこと等は可能ですが、野外に放すこと等は禁止されています。
最後まで責任をもって飼いましょう。
■ ウシガエル

 体長は12~18㎝程度
体長は12~18㎝程度
体色は緑色から褐色まで様々 虎斑模様が入ることが多い
背中に背側線なし
大きな鼓膜が特徴(オスは目より大きく、メスは目と同じくらい)
■ オオクチバス
 体長は30~50㎝程度になる
体長は30~50㎝程度になる
体は灰緑色で、背中側はやや黒く、腹側は白~黄色を帯びる
体の側面には、不規則な斑紋あり
口が大きく、耳よりも後ろ側まで割けている
■ ヌートリア
 頭から尻尾の付け根までは40~60㎝程度
頭から尻尾の付け根までは40~60㎝程度
尻尾の長さは30~40㎝程度
尻尾は細長く、毛がほとんど生えていない
全身が茶色
口の周りだけ白っぽい毛で覆われている
前歯は大きく、オレンジ色
■ ブルーギル

体長は20㎝程度になる
体は緑褐色で、10㎝ほどの細い縦縞模様あり
えらぶたにある、紺色の丸い模様が特徴
■ アゾラ・クリスタータ


水面上を浮遊する浮草
植物体全体に赤みがある
葉の表面に2~3個の細胞からなる突起が多い
根毛がある
※ 駆除する際には根から抜き、天日にさらし枯らしてから、ごみとして処分してください。
■ オオフサモ


水面より上まで茎をのばす
鳥の羽のような形で白色を帯びた緑青色の葉が1節に5~6枚ずつつく
※ 駆除する際には根から抜き、天日にさらし枯らしてから、ごみとして処分してください。
■ ナガエツルノゲイトウ


節から1対の葉
葉の先はややとがる
茎の中心は空洞
茎はなめらかでざらつかない
夏から秋に、小さな花が集まった球状花が咲く
※ 駆除する際には根から抜き、天日にさらし枯らしてから、ごみとして処分してください。
被害をふせぐために
一人ひとりが外来生物について考え、行動すれば被害拡大を防ぐこともできます。生き物を飼うときには、次の「外来種被害予防三原則」を守って行動しましょう。
「入れない」
生態系等へ悪影響を及ぼすおそれのある外来生物はむやみに「入れない」ようにしましょう。
「捨てない」
飼養・栽培している外来生物を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)ようにしましょう。
「拡げない」
既に野外で繁殖している外来生物を「拡げない」(増やさないことを含む)ようにしましょう。
植物の特定外来生物を駆除する場合は、原則、発見場所の管理者(所有者)が駆除することなります。
自前で駆除を実施できない場合は、駆除業者へ連絡してください。
関連リンク
- 日本の外来種対策|外来生物法【環境省HP】
https://www.env.go.jp/nature/intro/
- 外来生物・ヒアリ等に関する子ども向け啓発チラシ 【環境省作成チラシ】
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 環境課
-
-
電話番号:0855-25-9420
-