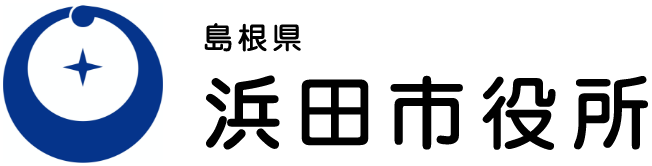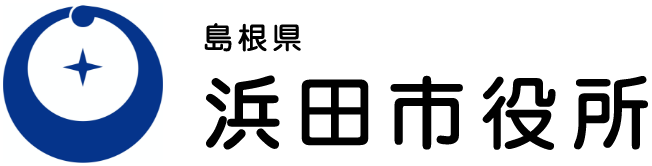| 会議名 | 第1回石見神楽保存・伝承拠点基本構想検討委員会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | 令和7年5月29日(木) 18時30分~20時30分 | |||
| 開催場所 | 浜田市総合福祉センター 会議室 | |||
| 会議の担当課 | 文化振興課神楽文化伝承室 | |||
| 議題 |
1 委員会の設置について 2 協議事項 ・会長・副会長の選任について ・会議の公開について 3 報告事項 石見神楽保存・伝承拠点基本構想検討委員会の検討事項について 4 意見交換 石見神楽の保存・伝承拠点に必要と考える機能や展示・活用方法等について |
|||
| 議事録 | 第1回石見神楽保存・伝承拠点基本構想検討委員会議事録(PDF/818KB) | |||
|
オンラインでの 公開・非公開 |
公開(会議の動画はこちら) | |||
配布資料
02_石見神楽の保存・伝承に関する提言書【資料2】(PDF/454KB)
03_石見神楽の保存・伝承に関する提言に係る参考資料【資料3】(PDF/952KB)
04_石見神楽保存・伝承拠点基本構想検討委員会の会議開催予定等【資料4】(PDF/336KB)
協議事項及び主な意見
1 協議事項
(1)会長・副会長の選任について
会長に島根県立大学の豊田知世氏、副会長に石見ケーブルビジョン㈱の福浜秀利氏が委員から推薦され、全会一致で承認された。
(2)会議の公開について
浜田市附属機関等の会議の公開に関する要綱に基づき、録画配信を異議なく承認された。
2 主な意見
|
内容 |
|
行政として、市内にある歴史的な資料を十分調査できる体制を整え、浜田に伝わる石見神楽がどういう歴史をたどってきたのかということを調査し、それについて文化財行政的な適切な措置、散逸を防ぐ対策をとっていく必要がある。また、調査した情報を行政だけで持っておくのではなく、広く市民、観光客等に対して発信をしていく必要がある。 |
|
拠点については、石見神楽のことだけでなく、浜田の歴史文化が広く知れる、石見神楽に関心がない人など広く市民の方に開かれるような拠点であることが望ましい。そういう意味では以前から話のある、郷土資料館と合わせることが良いのではないか。 |
|
施設としては、何度も訪れたくなることが必要。企画展示や、石見神楽を深く知ることのできる講演会、講座のようなものがあると良い。また、面の絵付け体験、採物を作る体験など、ワークショップや体験型のプログラムを作り資料館・博物館に訪れるハードルを下げることができればよい。 |
|
行政としてやるべきことの1つは保存。資料が散逸する前に所在の確認調査を行い、それを施設で保管する機能、役割が必要。また、そういった文化財は市民共有の財産であるため、市民と共有することが重要。 |
|
市民一人ひとりが、拠点をとおして、石見神楽を通じた地域社会のことを学習することにより、地域の誇りを持つことに繋がる。それがまちづくり大きな推進力になっていくことを期待したい。 |
|
石見神楽のものづくりをはじめとする浜田市で培われてきた様々な石見神楽文化を、市民をはじめ多くの人に学んでもらえ、後世に間違いなく継承する場であるということが重要。 |
|
舞、ものづくり、歴史などの石見神楽の文化について、分散して扱うような拠点の場ではあってはならない。 |
|
今後50年、100年先を考えると、現在の浜田市が誇る50以上の神楽団体が残っているかと考えたとき、おそらく残っていない。そうなったときに、地域から寄贈を受けた神楽用具などを売るとか、捨ててしまうということは、石見神楽の地域として余りにも悲しいことである。そういうものを収蔵し、活用が終わったときには地域へ返してあげるような機能があれば良い。また、石見神楽に関する調査を行うに当たっても、収蔵施設がなければ、調べてどうするのかと感じる。 |
|
浜田における石見神楽は、伝統芸能であるとともに、大切な観光資源であることも事実である。 |
|
石見神楽を創り出したまちとして、拠点については独立特化したものが望ましい。また、郷土資料館との複合化というような意見もあるが、郷土資料館よりも浜田城資料館の方が親和性はあると感じる |
|
浜田のプライドをかけて、神楽関係者だけでなく、まずは地元の人、石見神楽に興味がなかった人でも足を運んでくれるような場を目指すべき。 |
|
昔は、週末に買い物に出たりすると、どこからかお囃子が聞こえてきて、行ってみると石見神楽をしていて、多くの人が集まっていた。また、最近少なくなった土曜夜市も、必ず石見神楽とセットであったため、拠点についてはそのような場となってほしい。 |
|
石見神楽の変遷してきた流れを記録として残すということが重要。 |
|
石見神楽は舞い手や楽人だけでなく、裏方の人もいないといけない。そういうことを知ってもらうのが拠点として大事である。 |
|
神楽上演のスケジュールを調整する役割を担ってほしい。 |
|
SNSを使って社中員の募集をしているが、中々情報発信がうまくできていないと感じている。拠点で石見神楽団体の紹介をすることにより、少しでも興味を持ってもらえると良い。 |
|
衣裳を入れる箱など、用具の保管に広い面積を使っている。そういった用具を拠点で管理し、風通しを行うなど、現状維持できる状況にしてもらって、それについては展示をしても良いことにするような関係性が理想である。 |
|
石見神楽の存在は知っているが、敷居が高いと感じている人、見ても分からないと感じている人などが多くいる。この拠点ができることによって、そういう人を取り込めたら良い。 |
|
拠点については、ワクワクするものが必要である。自分たちが子どものときは祭りに行くと、石見神楽も縁日も行っており、子どもにとってパラダイスな状況で育ってきた。今の子どもたちにもそれを体験させたい。また、それを連れてくる保護者が、石見神楽の面白さを再認識できれば良い。 |
|
石見神楽を舞う側の立場からすると、可能であれば雨が当たらないなど荷物が入れやすくて、シャワールームがあれば良い。そういう拠点であれば、舞い手としてもやる気が上がる。 |
|
例えば東京公演をホールで行って、それを観たお客さんが浜田に石見神楽を観に来たときには、やはり舞殿で観てもらうべき。舞殿は夜通し舞ができるよう完全防音の設備とし、舞台も舞殿から大蛇8頭が出ることができるようなステージへ転換できるような完全に石見神楽に特化した建物にしてほしい。 |
|
浜田の石見神楽団体全部の用具を受け入ることができるような収蔵庫をつくってほしい。 |
|
内容やストーリーの説明が必要。最初に物語の説明があることもあるが始まると、どういう展開、状況なのか全く分からないことがあり、面白くない思う時がある。口上の現代語訳や漫画など色々な工夫ができるのではないか。また、石見神楽に関する豆知識みたいなものを知れることができると良い。 |
|
収蔵するだけでなく、バックヤード見学や体験型という形で収蔵した衣裳を着ることができるような施設であれば面白い。 |
|
収蔵した衣裳などを、衣裳が足りていない団体に貸し出しすることができたら双方に利益がある。 |
|
地域に根差した博物館機能を考えいくのか、それとも、博物館機能の中でも、観光的なところに比重を置いていくのかの視点を考える必要がある。 |
|
子どもたちが石見神楽に引き込まれる入り口は、格好の良さと気品の高さである。それを展示なり活用なりで上手く見せていく必要がある。 |
|
拠点においては、コーディネーター、学芸員があってこそ、全てが生きてくる。ハブ機能的に石見神楽団体、市民、専門家をつなぐのが、コーディネーター、学芸員の大きな仕事である。 |
|
石見神楽団体や、神楽産業の未来を守ることが絶対的なミッションである。そのための、この拠点が持つ効果をきちんと数値化するために、そこを担う組織を検討する必要がある。また、指定管理するにしても、どこでも運営できるわけでなく、ある程度専門性を持った人が入ることが必要。 |
|
拠点の候補地を示した方が検討する上でイメージがしやすいのではないか。 |
|
石見神楽について、とても魅力的な文化と思っているが、これまで知る機会がなかったので、その勉強がでればより魅力的なものになる。また、石見神楽を通して、神楽関連産業の歴史や石見神楽を含めた暮らしや歴史などの浜田市のことをもっと知れるような施設となれば良い。 |
|
石見神楽に関する資料が確実に健全な状態で、将来にわたり保存できることが重要。健全な状態であるからこそ、活用できる。 |
|
展示については、全国から見た石見神楽の位置付けがわかるような展示とするべき。石見神楽は一地方のローカルな芸能であるが、明治以降はローカルでありながら、広く影響を持つグローバルな存在になっている。そのようなことを含めて、幅広い視点での展示としてほしい。 |
問い合わせ先
浜田市殿町1番地
浜田市教育部文化振興課神楽文化伝承室
電話 0855-25-6301
e-mail bunka@city.hamada.lg.jp
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 教育部 文化振興課
-
-
電話番号:0855-25-9730
-