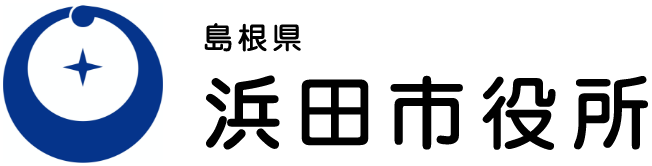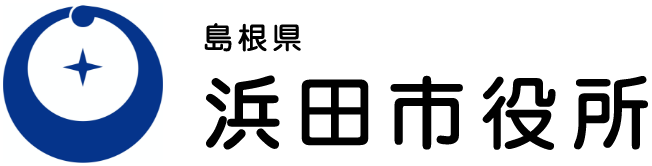| 会議名 | 第3回石見神楽保存・伝承拠点基本構想検討委員会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | 令和7年8月8日(金) 18時30分~20時30分 | |||
| 開催場所 | 浜田市立中央図書館 多目的ホール | |||
| 会議の担当課 | 文化振興課神楽文化伝承室 | |||
| 議題 |
1 協議事項 ⑴ 保存・伝承拠点のあり方と必要な機能の整理について ⑵ 具体的な取組方針や実現手法などに関する意見交換(グループワーク) |
|||
| 議事録 | 第3回石見神楽保存・伝承拠点基本構想検討委員会議事録(PDF/610KB) | |||
|
オンラインでの 公開・非公開 |
公開(会議の動画はこちら) | |||
配布資料
【資料1】石見神楽保存・伝承拠点基本構想検討委員会資料(PDF/2MB)
主な意見
グループワーク意見(Aグループ:豊田会長、藤原委員、浅沼委員、堀尾委員)
テーマ「展示機能」
|
機能 |
目標及び取組方針(案)・実現手法(案) |
|
|
展示機能 市民や来訪者が石見神楽の魅力と奥深さを多角的に理解できるように表現・公開する機能
|
【目標】 石見神楽の全てがわかり、「石見神楽を創り出したまち浜田」を正しく理解し、市民が誇りを持つ |
|
|
【取組方針(案)】 ・常設展示と企画展示を組み合わせて、何度訪れても発見がある構成とする。
・解説やナビゲーションには多言語対応や子ども向けの視点も取り入れ、幅広い層に対応する。
・実物資料とデジタルを活用した展示を組み合わせる。
・研究成果を展示や教育、出版、ウェブ等で発信し、広く活用する。
・実物資料や映像、音、ストーリーパネルなどを活用し、舞や奏楽に加えて裏方の職人技にも焦点を当てた展示を行う。
・見るだけでなく、臨場感があったり、触れたり聴いたり五感で体験することのできる展示とする。
・全国の神楽から見た石見神楽の位置づけが分かるような展示もあれば良い。
・なぜ浜田で石見神楽がこんなにも普及しているのかが、分かるような展示もあれば良い。
・各神楽団体の違いが分かるような展示、情報発信もあれば良い。 |
【実現手法(案)】 ・企画展示室の確保 ⇒企画展示室は必要と思うが、企画展は学芸員にとってかなりの負担となることから、適正な規模の展示室にすること。また、企画についても「石見神楽」のみではなく幅広とした方が良い。また、学芸員は1人では難しいと思われる。 ⇒常設展のコンセプトなどは委員会を立ち上げて検討する方法もある。 ・基本ターゲット(子ども・大人?) ⇒大人でも難しい解説は読まない人も多い。歴史系の博物館では基本的に小学校6年生が理解できるようなレベルで考えている。 ・多言語解説 ⇒多言語解説は必要であるが、多くの言語の解説があると、雑多に感じる。実物の解説は日本語と英語くらいに留めて、他の言語はQRコードなどで対応する方法もある。 ・面、衣裳、蛇胴など神楽用具の実物の展示 ・デジタル技術(タブレットやスマートフォン)を使用した展示 ⇒デジタル技術を使用した展示は、ランニングコストや故障の問題がある。 ⇒展示をデザインする専門の人がいるので、そういった人に頼んでセンス良くまとめる方法もある。 ⇒東京国立博物館は、概ね実物展示である。
・舞台裏を支える人々に着目 ・製作過程の展示、制作場所の映像 ・県など色々なところが作っている映像資料などを集約する ・プロローグでの臨場感ある体験 ⇒派手な演出は必須でなく、展示の見せ方で、施設に入ったときのワクワク感を演出することもできる。 ・実際に面にさわったり、太鼓を叩いてみたりという作る・演じるの疑似体験 ⇒触れることのできる展示が必要。楽器や衣裳蛇胴など。一方で、演じる体験はスペース的に難しいのではないか。 ⇒採り物を作るワークショップなどがあると良い。 ⇒ワークショップ、イベント、講演などができる多目的室のような部屋があれば良い。
・市民が石見神楽について疑問に思っていることを集約して情報発信する。 |
|
グループワーク意見(Bグループ:福浜副会長、仲野委員、柿田委員、川本委員)
テーマ「教育・普及機能」
|
機能 |
目標及び取組方針(案)・実現手法(案) |
|
|
教育・普及機能 市民の理解と誇りを育み、次世代への伝承につなげる機能 |
【目標】 学校のふるさと郷育などで利用できるとともに、市民が何度も利用する |
|
|
【取組方針(案)】 ・子どもや若者が石見神楽に親しむワークショップや体験教室を開催し、演じる・作る・知る機会を提供する。
・学校教育と連携し、ふるさと郷育として石見神楽(継承する人物など)を取り扱う際のサポートをする。 ⇒学校教育の中で行うのであれば、各学校でバラバラに行うのではなく教育員会としての方針や必要な予算の確保が必要。 ⇒学校教育だけでなく神楽好きの子どもたちの拠り所となるような場所となれば良い。社中に入ってなくても神楽を舞いたいという子はいるはず。 ・子どもだけでなく大人に向けた解説講座や公開練習なども展開し、世代を超えた普及を図る。 ⇒講座については、初心者向けや上級者向けなどレベルを分けて開催するべき。 ・SNSやメディアを通じて、石見神楽の「かっこよさ」やストーリー性を発信し、特に若年層の関心を喚起する。
・石見神楽の要素を活かした商品開発や映像・アートとのコラボレーションなどにより、裾野の拡大を図る。
・部活動の地域移行の受け皿としての拠点となってほしい。
・周辺施設との連携 |
【実現手法(案)】 ・担い手やプログラムの構築 ・体験場所(練習場や工房)の確保 ⇒衣裳を着たり、面を付けたりができる体験は必要。 ・コンテンツの作成、担い手の確保 ⇒拠点施設における教育普及で舞い手や神楽関連産業の担い手を確保するのは難しい。
・専門家との連携、コーディネイターの確保 ⇒地域との連携が必要。「どんちっちサポートIWAMI」との連携や、「郷土資料館友の会」の神楽版のような市民団体が立ち上がると良い。また、そういったところへの支援も必要。
・石見神楽を取り扱っているアーティストの方とコラボする。 ・福祉分野とのコラボ(フレイル予防としての舞など) |
|
グループワーク意見(Cグループ:小川委員、塚本委員、梅津委員、丸山委員、大下委員)
テーマ「伝承機能、交流機能」
|
機能 |
目標及び取組方針(案)・実現手法(案) |
|
|
伝承機能 「伝統的な舞の文化」や石見神楽団体、石見神楽関連産業、ものづくり技術を後世に伝承する機能 |
【目標】 石見神楽文化・舞や道具に関する技術の伝承、企業・団体の伝承(後継者の確保・育成) |
|
|
【取組方針(案)】 ・「石見神楽文化」を明確化し、石見神楽を取り巻く歴史や観る側のマナーなどが学べる
・各神楽団体において古くから継承されている伝統的な舞を後世に伝承する。
・夜明け舞など多くの演目を舞うことができるための環境を整備する。
・石見神楽団体、石見神楽関連産業の後継者を育成・確保するための取組を行う。
・子どもたちのあこがれの舞台としての拠点とする。 ※子どもたちは多くの人がいる場で、主役として舞うことを理想としている。 |
【実現手法(案)】 ・展示機能の中で検討
・いつでも練習ができる場の確保
・展示や教育・普及機能の中で検討
⇒伝承機能の取組方針は舞殿で舞を見てもらえれば、全て網羅することができる。まずは興味を持って、好きになってもらうことが重要。
・定期的な公演ができる舞殿 |
|
|
機能 |
目標及び取組方針(案)・実現手法(案) |
|
|
交流機能 人と人、人と文化をつなぎ、石見神楽を通じた地域内外のネットワークを築く機能 |
【目標】 多くの市民、市外の方に石見神楽の魅力を知ってもらう |
|
|
【取組方針(案)】 ・地元神楽団体の交流や合同公演、体験イベントを通じて相互理解を進める。
・舞殿や工房など、来訪者と演者・職人が出会う場を設け、日常的な交流を生み出す。
・拠点自体が石見神楽に関する情報のハブとして機能し、各地の活動や知見が集まり、共有・発信される場となる。
・他地域や異分野とのコラボレーションや、新たな担い手が創造的に関われるフィールドを提供し、石見神楽の新たな挑戦と誇りを生み出す。
・石見神楽に関わる技術や資源を活用したビジネス化・観光化を図り、地域経済の活性化にも寄与する。
・石見神楽に特化した観光と文化継承をする拠点 ⇒ランニングコストのことを考えると観光誘客も考えるべき
・舞殿は神楽に特化したものが良いが、他の目的で利用もできる |
【実現手法(案)】 ・伝統的な舞を可能な限り、伝統的な空間で見せることができる場 ⇒各団体がしたいことが全てできる舞殿。夜明け舞もできるし、全ての演目や、周年記念の公演などもすることができる。 ⇒大きな体育館の中にお宮が建っているようなイメージ ⇒三方から見ることができる舞台 ⇒舞台は3間×3間(約30㎡)をベースに、可動式で広くすることができればよい。 ⇒蛇胴や衣裳が当たるような近さの席 ⇒金・土・日の定期公演としたい ⇒本物の舞は各地のお祭りで見ることができるが、あくまでも地域の氏子のためのものである。奉納スタイルを見せることができる舞殿とする ⇒飲食もでき、販売ブースも設ける ⇒取捨選択できる解説(イヤホンなど) ⇒三宮神社はあくまでも借りているもので、いつまでも使えるかは不明である。 ・新しい挑戦をみせることができる場 ⇒音響や照明設備によって対応する。 ・交流などを促進するレセプションルームなどの確保
・民間企業等と連携
|
|
問い合わせ先
浜田市殿町1番地
浜田市教育部文化振興課神楽文化伝承室
電話 0855-25-6301
e-mail bunka@city.hamada.lg.jp
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 教育部 文化振興課
-
-
電話番号:0855-25-9730
-