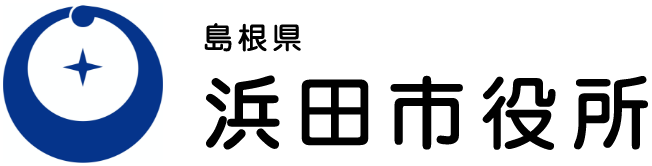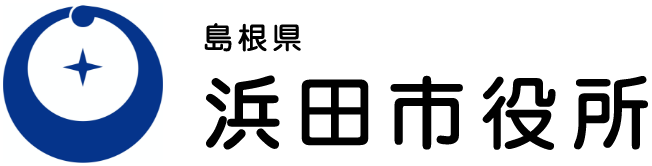| 会議名 | 第4回石見神楽保存・伝承拠点基本構想検討委員会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | 令和7年9月19日(金) 18時30分~20時35分 | |||
| 開催場所 | 浜田市立中央図書館 多目的ホール | |||
| 会議の担当課 | 文化振興課神楽文化伝承室 | |||
| 議題 |
1 協議事項 (1) 保存・伝承拠点のあり方の整理について (2) 保存・伝承拠点の機能ごとの具現化の方向性について |
|||
| 議事録 | 第4回石見神楽保存・伝承拠点基本構想検討委員会議事録(PDF/688KB) | |||
|
オンラインでの 公開・非公開 |
公開(会議の動画はこちら) | |||
配布資料
第4回石見神楽保存・伝承拠点基本構想検討委員会資料(PDF/2MB)
主な意見
|
機能 |
内容 |
|
① 収集・保存機能について |
・収蔵庫について1箇所に全部を集約するのは、反対である。歴史資料は神楽の歴史を伝えているだけではなく、その地域の歴史を伝えているものなので、1か所に集めてしまうと持っていかれたところからすると、歴史が消えてしまう。例えば、統合して使われなくなった学校とかでも十分維持管理ができる。 ・人がいなくなって管理ができないことになれば、どうしても1か所に集めざるを得ないこともある。神楽の用具も、地域から寄付を受けて、地域のものとして大事にされているものもあれば、団体が購入しているものもあるため、その辺も色々関わってくる。 ・浜田市は支所展示ということで、それぞれの支所で地域の古文書や公募資料なども展示して、結構好評だという話も聞いている。そういった支所展示でも神楽の展示もあわせて行うと、全体として神楽の意識づけができるのではないか。 ・石見神楽を見る側の文化も重要だと思う。例えばお年寄りが神楽を観に行く日には、どんな気持ちだったかとか、どういうものを用意して行ったなども収集して、記録をアーカイブ化すると良い。 ・保存する環境が整っていない団体や衣裳が多すぎて保管が難しい団体の衣裳を収集して管理の手伝いみたいなことができたら良いのではないか。また、収集する際に他団体に対して貸し出しの可否を確認して、用具が足りていないところに貸し出すことができれば良い。 |
|
② 調査研究機能について |
・設備としては、基本的なもの(パソコン、机など)が揃っていると調査は出来る。あとは、全国の神楽に関する図書類や資料、展示用の写真を撮る写場などがあると良い。 ・調査用の部屋はあると良い。 ・神楽で生活していける人(拠点における学芸員や、拠点のスタッフ、舞い手など)を浜田から出すことが重要 ・大学に入って初めて来て、石見神楽を知って、石見神楽が好きで浜田に残りたいという学生も一定数いる。専門的な知識はそこまでないかもしれないが、熱意があり、石見神楽を何とかしたいというような、フットワークの軽い若い人たちが活躍できるような場所があると良い。 ・人材という面で、学校を退職された職員の方は、ふるさと郷育の面でも、非常に重要な役割を果たしてもらえるのではないか。 ・今回、非常に多岐にわたる項目が上がりすぎていて、一体誰がやるのかということになると、現実的にはどうしても学芸員が中核にならざるを得ない。そういったところを考えて、ソフト的なところもハード的なことも考えていかないと、本当に幾つもいろいろ出たが、実際にやるときに多分できない。そのあたりを、今後、これからこの構想を絞って検討していく中で考えなければならない。 |
|
③ 展示機能(体験・学習)について |
・今回の資料を見ると、デジタルコンテンツが多いように感じ、そうすると維持管理が大変である。デジタルコンテンツをまんべんなく配置するのでなく、ここぞのところで使うことが必要。 ・導入の部分で「神楽って何」というところから始めるべき。地元の人は何となく分かるかもしれないが、他所には多くの種類の神楽があるため、そういうところから導入した方が良い。 ・色々な体験項目が書いてあるが、展示の中での体験なのか、体験専用の部屋、場所で行う体験なのかが、混ざっているように感じる。 ・資料館の観覧者は、一般的に最初は集中力があるが、半ばくらいから読み物などを読まなくなる。最初に体験を持ってきてしまうと、集中できるタイミングを逃す。 ・この施設の目的が保存と伝承であるため、「5考える」の項目が重要である。博物館などは、情報を一方的に受け取るだけになっているため、考えるという部分が教育としてもすごく重要である。拠点施設に期待するのは知的な理解というよりも、皆がこの文化を今後どのように残し、継承していくかということを、ここでしっかり考えるような仕掛けを作らないと次に繋がらずそれができなければ、ただの観光施設になってしまう。 |
|
④ 教育・普及機能について |
・石見神楽の保存・伝承の拠点として、音の問題は非常に重要。石見神楽というのは音というのが非常に重要な要素だと思っており、拠点という一つの空間、エリアで、それをどう制御したり、うまく使ったりするかというのは、これから展示にしても教育・普及にしても具体的に考える段階で、きっちり検討する必要がある。 ・体験について、体験といってもレベルがあって、初めて浜田に来た人が体験する場合、浜田市内の子どもたちが体験する場合と、もう一つ、この拠点のポイントとして担い手というところがあるため、これをするための体験、あるいは学習、伝承、そういったことは、ある程度、この基本的な考えの段階でレベルをしっかり設定する、考えておくことが必要。 ・学芸員と市民の皆さんの連携が、この拠点の中で一番重要なポイントである。これがきちんとできないと、保存、収集、展示、教育・普及が多分何も動かないということになる。学芸員をどのぐらいの体制で置くのかによって、今ここで議論している内容がどこまでできるかが決まってくる。 ・小学校の課外授業で、色々な学校の児童が来るが、地元の子どもたちも、神楽の用具が和紙でできているとかを全然わかっていない状態。地元で生まれ育った子は、もう少し勉強する機会があっても良い。 ・学芸員とは別に、石見神楽のことが本当に分かる専門職員の育成が必要。 |
|
⑤ 交流機能について |
・特化したものが必要というのは当初から言われている。神楽以外の利用のために作るわけでなく、神楽をするための施設を別のことでも使えるというイメージ。 ・椅子の座席も必要。 ・天蓋の高さも団体によって違うので調整可能としたい。 ・花火が使えるような防火設備としたい。 ・練習できる場というのが、練習場に道具も全部持っていくとなると、拠点から遠い団体は難しい。例えば、旭町の方から、市内に練習に来るとなると、道具を用意して、練習に行って、帰って道具をしまうとなると1時間練習するのに、準備等含め4時間かかる。 ・石見神楽を観る側に、どういうふうに神楽を見ていいのかを発信できたらよい。また、先日、テレビ番組で紹介された石見神楽面を玄関に飾る風習なども、発信すると神楽を全国的に周知するのに良いのではないか。 ・図だけを見ると体育館に稼働ステージが出てくるような感じだが、入った際に舞殿の雰囲気が無いと特化したものとは言えない。神楽以外にも使えるのが先行してしまうと、神楽の舞殿ではなくなる。 ・観客200人という想定は、例えばコロナの想定したり、空間を少し開けたり、できるだけ近くで見ていただくということでその数字となっている。それが300人でも良いとは思うが、あまり広すぎるとそれはまた違うとも思います。 ・利用料の関係で、第1ターゲットが浜田市民で何回か来てもらうことを想定するのであれば、市民割とか、年間パスポートみたいなものも取り入れておいた方が、何度も訪れることにつながる。 ・文化施設とすれば、舞の伝承をまずは市民にわかってもらうということが一番大事。一方で石見神楽は浜田にとって、大変重要な集客のアイテムである。文化が突出するか、観光が突出するということではなくて、この両輪をきちんとやってもらって本物が営まれるところに人がやってくると思う。 |
問い合わせ先
浜田市殿町1番地
浜田市教育部文化振興課神楽文化伝承室
電話 0855-25-6301
e-mail bunka@city.hamada.lg.jp
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 教育部 文化振興課
-
-
電話番号:0855-25-9730
-