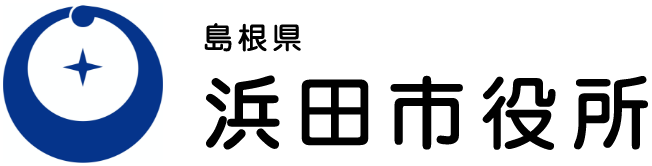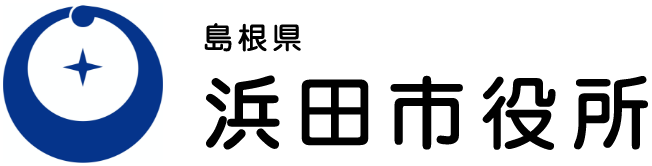個人住民税とは、市民税と県民税を合わせたもので、住民にとって身近な行政サービスの費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性質の税金です。
市民税・県民税は、いずれも均等割と所得割から構成されています。
● 均等割:税金を負担する能力のある人が均等の額を負担します。
● 所得割:その人の所得金額に応じて負担します。
個人住民税を納める人(納税義務者)
|
納税義務者
|
所得割
|
均等割
|
|
浜田市内に住所がある人
|
○
|
○
|
| 浜田市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する人で、市内に住所を有しない人 | ― | ○ |
※ 1月2日以降に他市町村に転出されても、1月1日現在、浜田市内に住んでいれば、その年度の個人住民税は浜田市に納めていただくことになります。
※ 1月2日以降に亡くなられた場合も、その年度の個人住民税が課税され、相続人に納税義務が承継されます。
均等割(令和6年度より変更)
| 区分 | 平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度 | 令和6年度以降 | |
|
均等割 (個人住民税) |
市民税 |
3,000 円 |
3,500 円 | 3,000 円 |
| 県民税 | 1,500 円 | 2,000 円 | 1,500 円 | |
| 森林環境税 | 国税 | ― | ― | 1,000 円 |
| 合計 | 4,500 円 | 5,500 円 | 5,500 円 | |
所得割
所得割は前年の所得に応じて負担していただく税で、均等割とは異なり、所得金額と所得控除額を基に計算されています。
( 所得金額 - 所得控除額 )× 税率 - 税額控除額 = 所得割額
| 税率(総合課税分) | |
|
市民税
|
県民税 |
|
6%
|
4%
|
※ 分離課税分に対する税率はこのとおりではありません。(分離課税の税率)
個人住民税が課税されない人
(1)均等割・所得割のどちらも課税されない人
● 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
● 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下の人
(2)均等割が課税されない人
● 同一生計配偶者・扶養親族のいない人:38万円
● 同一生計配偶者・扶養親族のいる人 :28万円 ×( 本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族 )の人数 + 16万8千円 + 10万円
|
扶養人数(※1)
|
合計所得金額
|
【参考】給与収入金額
|
|
0人
|
380,000円
|
930,000円
|
|
1人
|
828,000円
|
1,378,000円
|
|
2人
|
1,108,000円
|
1,683,999円
|
|
3人
|
(※2) 1,388,000円
|
2,099,999円
|
※1 扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満の年少扶養親族も含む。)の合計数です。
※2 扶養人数が1人増えるごとに、280,000円加算されます。
(3)所得割が課税されない人
● 同一生計配偶者・扶養親族のいない人:45万円
● 同一生計配偶者・扶養親族のいる人 :35万円 ×( 本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族 )の人数 + 32万円 + 10万円
|
扶養人数(※1)
|
総所得金額等
|
【参考】給与収入金額 |
|
0人
|
450,000円
|
1,000,000円
|
|
1人
|
1,120,000円
|
1,703,999円
|
|
2人
|
1,470,000円
|
2,215,999円
|
|
3人
|
(※2) 1,820,000円
|
2,715,999円
|
※2 扶養人数が1人増えるごとに、350,000円加算されます。
申告
1月1日(賦課期日)現在で浜田市内に住所がある人は、毎年3月15日までに、前年中(1月から12月まで)の収入を市へ申告してください。 ただし、次の人は申告の必要がありません(控除の追加・変更等がない場合)。
● 所得税の確定申告をした人
● 前年の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所へ提出されている人
● 前年の所得が公的年金所得のみの人
● 浜田市内に居住する親族の税法上の扶養となっている人
また、収入がない場合でも、国民健康保険などの軽減制度が適用されないことや、所得課税証明の発行ができないことがあるため、収入がなかった旨の申告を提出していただく必要があります。
詳しい内容はお問い合わせください。
納税方法
|
区分
|
納税方法
|
|
普通徴収
|
市役所から納税通知書が交付され、通常6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて個人で納税する方法 |
|
給与特別徴収
|
給与支払者(特別徴収義務者)が市役所から通知された特別徴収税額を、サラリーマン等の給与所得者の毎月の給与から天引きし、6月から翌年5月までの年12回に分けて納税する方法 |
| 年金特別徴収 |
年金保険者が市役所から通知された特別徴収税額を、年金所得者の年金から支払時に天引きし、納税する方法 |
(注1)合計所得金額
繰越控除を適用する前の次の金額の合計額です。
● 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
● 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
● 退職所得金額 (分離課税の対象となる退職所得は除く)
● 山林所得金額
● 【分離課税】土地・建物等の譲渡所得の金額(特別控除前)
● 【分離課税】上場株式等に係る配当所得等の金額
● 【分離課税】株式等に係る譲渡所得等の金額
● 【分離課税】先物取引に係る雑所得等の金額
(注2)総所得金額等
合計所得金額に繰越控除を適用した後の金額です。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 税務課
-
-
電話番号:0855-25-9230
-